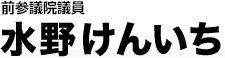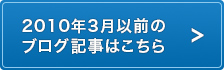- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
衆議院総選挙を前にして
2012.12.03
衆議院総選挙を前にして政党が離合集散している。一時期は14~15に上っていた政党が、いくつかのグループに収斂してきたような感がある。選挙目当てといえば選挙目当てには違いないが、小選挙区制度の下ではある程度必然の動きのようにも思える。
そもそも小選挙区制度というのは二大政党に圧倒的に有利な制度である。小選挙区というのは「1位になった者だけが当選」という仕組みである。中小政党が民主党、自民党の候補を押しのけて1位になることは至難の業である。
3年前の総選挙を見てみると300小選挙区のうち民主党と自民党という二大政党のいずれかが勝利した選挙区は285に上っている(注1)。逆に言うと二大政党以外の候補者が小選挙区を制したのはわずかに15選挙区にすぎない(注2)。小選挙区制度が導入される時、「政権交代可能な二大政党制を作る」ことが大義名分として喧伝されたが、幸か不幸かそうした状況が出現しているのは事実である。
ただでさえ勝ち抜くことが難しい小選挙区にいわゆる第三極が複数立候補すれば、さらに当選確率は下がる。票が割れてしまうからである。そこでなるべくお互いにぶつからないようにするというのは、選挙戦略上は理解できる。そうした協力をより一歩進めると政党同士の合流・合併につながっていく。その具体的な表われが「日本維新の会」と「太陽の党」の合併であり、嘉田新党(日本未来の党)への小沢一郎氏や河村たかし氏らの合流なのだろう。
こうした動きは選挙に勝つという一点からみれば当然のことである。しかしそれも行き過ぎると野合である。みんなの党は常に政策本位を掲げてきた。いかに選挙のためとはいえ基本政策を棚上げして合流・合併することは避けてきたつもりである。そのため今回の総選挙は単独で戦うことになった(他党と候補者を推薦する可能性はあるが)。
小選挙区制の下で中小政党が単独で戦うことはなかなか難しいのは先に述べてきた通りである。しかし右往左往せずに筋を通す政党が一つくらいあっても良いのではないかと思っている。
心ある方々の御理解・御支援をいただければ幸いである。
注1)総選挙における300小選挙区の獲得議席は、
二大政党 うち民主党 うち自民党
2003年総選挙 273 105 168
2005年総選挙 271 52 219
2009年総選挙 285 221 64
注2)前回総選挙で二大政党の候補者以外で小選挙区で勝利した主な例は、
渡辺喜美(栃木3区・みんなの党)、江田憲司(神奈川8区・みんなの党)、中村喜四郎(茨城7区・無所属)、辻元清美(大阪10区・社民党=当時)、平沼赳夫(岡山3区・無所属=当時)、亀井静香(広島6区・国民新党=当時)
BS朝日『ごごいち!ニュースキャッチ』出演
2012.10.22
水野賢一事務所です。
水野賢一がテレビに生出演いたしますので、
ご案内申し上げます。
2012年10月23日(火)13:00-14:00
BS朝日『ごごいち!ニュースキャッチ』
※13:10~13:30(目処)のコーナーに出演します。
《主な内容》
○『“近いうち”解散はいつ?臨時国会召集は・・・』をテーマに、民主、自民、公明、みんなの党、それぞれ参議院論客者が集まり討論形式でじっくり話を進めていく予定です。
是非ご覧下さい!
千葉テレビ『NEWSチバ930』出演
2012.10.17
水野賢一事務所です。
水野賢一が千葉テレビ『NEWSチバ930』に出演
いたしますので、ご案内申し上げます。
2012年10月19日(金) 21:30-
千葉テレビ 「NEWSチバ930」
《主な内容》
○国政の現状認識
○解散時期について
○総選挙に向けた活動
ぜひご覧下さい!
消費税増税法案の成立について
2012.08.17
消費税増税法案の成立について
~民自公三党による国会運営に抗議!~
◆増税法案の成立
「社会保障と税の一体改革関連8法案」が成立した。簡単に言えば消費税増税法案が成立したということである。これで消費税率は2014年4月から8%に、翌2015年10月には10%に上がることが確定した。
みんなの党はこの増税法案には一貫して反対だったが、賛成派の民主党、自民党、公明党の三党の数に押し切られた形になる。とはいえ増税賛成の三党の中にも思惑の違いがあった。早期解散を求める自民党は「解散の言質を取り付けるまでは簡単に賛成とはいえない」という姿勢を取ったので、採決直前の野田・谷垣会談まで法案の成否は不透明だった。
◆各党の立場
この間の各党の立場を整理してみると次のようになる。みんなの党は増税には反対、解散は要求するというものだったので「増税なし・解散あり」の立場だった。与党・民主党は「増税あり・解散なし」という姿勢だった。解散すれば惨敗の恐れがある以上、当然のことだろう。
他方、自民党は「増税あり・解散あり」であり、小沢一郎氏の新党(国民の生活が第一)は選挙基盤の弱い新人議員が多いため「増税なし・解散なし」の立場だったと推察される。表にすれば以下の通りである。
増税法案 衆議院解散
民主党 賛成 なし
自民党 賛成 あり
生活(小沢新党) 反対 なし
みんなの党 反対 あり
民主党としては増税法案だけ成立させて、解散は先送りというのが理想だっただろうが、ねじれ国会の中では自分たちの主張だけでは法案が通らない。そこで同じ増税派の谷垣自民党総裁と話し合った末、「近いうちに」解散することで折り合ったわけである。しかし国民生活に密着する重要法案を成立させてから「近いうちに」解散するという方針自体が間違っている。先に解散をして国民に信を問うてから重要法案を審議するというのが筋だろう。まして前回総選挙の時の民主党マニフェストでは増税を約束していないのだからなおさらである。
◆みんなの党の立場
みんなの党はなぜ増税に反対したのか。手続きと内容に大きな問題があるからである。手続き上の最大の問題は、マニフェスト違反ということである。ただこれについては多くの人が論じ尽くしているので、ここではそれ以上触れない。
それ以外にも増税の前にやるべきことをやっていないということも指摘しなければならない。無駄遣いの温床とされる特別会計、特定財源、独立行政法人などにメスを入れることも不十分である。
しかも国会議員や官僚が身を削ることにも腰が引けている。「国民に負担を求める前にまず身を削るべきではないか」という批判の前に、確かに今年5月から国会議員歳費は12.8%カットされた。しかしこれは2年限定の措置である。消費税増税が恒久措置であるのに、なぜ身を切る方は2年限定なのかさっぱり分からない。ちなみにみんなの党は国会議員の歳費3割、ボーナス5割カットを主張し、そうした法案を過去6回にわたって提出しているが、残念ながら他党に黙殺される形で採決に付されることもないままたなざらしにされている。
増税法案は内容面でも問題がある。そもそもデフレ下での増税自体が経済学の理論に反している。さらに問題なのが税の使途である。当初、政府はこのように説明していた。「年々、社会保障費は伸びている。この社会保障費の伸びをまかなうには消費税増税しかない」。
ところが民自公三党の協議の中で、国土強靭化を名目に公共事業に使う余地まで出てくるようになった。「増税で財政にゆとりができた分をそちらに回すので、消費税そのものを公共事業に充てるのではない」という説明もあるが、結局は同じことである。当初の説明との整合性を問われるためにそうした苦し紛れの説明をせざるを得ないのだろう。
◆三党による国会運営を打破
最近の国会運営を見ると民自公の三党が合意をすればあとは何でもありという姿勢が多くみられる。道理が通らなかろうが何であろうが、あとは問答無用で押し切るという姿勢である。衆参両院のいずれでも民自公三党を合計すると議席の占有率は約8割を占めている(最近、民主党から離党者が相次いでいるため占有率は下がったとはいえいまだに8割はある)。それだけにこの数の力で何でも可能になってしまう。
ただこれを嘆いているだけでは始まらない。近いうちに予想される総選挙においてみんなの党として躍進することで、三党による国会運営を打破すべく力を尽くさなければならないと感じている。
原子力発電について
2012.05.24
原子力発電について
~トイレなきマンションとは?~
◆経営責任はどうなる?
昨年に続いて2年連続で電力不足の夏になりそうだ。とはいえ昨年と今年では違いもある。昨年の供給力不足の原因は東日本大震災で発電所が甚大な被害を受けたことだった。そのため電力使用制限令が出されたのは東京電力と東北電力の管内だった。それに対して今年最も深刻な電力不足が叫ばれているのは直接の被災地ではない関西電力管内である。原子力発電所がすべて停止したためである。原発は関西地域だけでなく全国すべてで停止しているが、関西電力はとりわけ原発依存度が高かった。そのため電力需給が特に逼迫しているわけである。
「だからこそ原発再稼働が必要だ」という声も上がっている。しかし「ちょっと待った」と言いたい。そもそも原子力発電というのはリスクが高い電源である。それを知りながら積極的に導入していたのが関西電力である。今回、それが裏目に出たことになる。そうである以上、経営者の判断が正しかったのかどうかが問われるのは当然だろう。東電幹部が事故の責任を問われるべきならば、関電幹部は経営責任を問われるべきなのである。現に原発を一基も設置していない沖縄電力は昨年も今年も電力不足とは無縁である。そうした中、安価な電源だから(本当に安価かどうかはかなり疑問があるが)と多くの原発を立地したのが関電だった。この責任を明確にしないまま再稼働の必要性だけを力説しても説得力に欠けると言わざるを得ない。
◆原発からの廃棄物
さて関電の話から離れて今後の原発政策全体を考えてみたい。みんなの党は脱原発を打ち出している。もちろんその背景には事故の危険性ということもある。だが事故だけが原発の問題ではない。仮に安全に操業したとしても原発の稼働は確実に将来に大きなツケを残すことになる。放射性廃棄物というツケである。私自身はむしろこの点こそ原子力発電の最大の弱点だと考えている。
原子力発電の燃料は基本的にはウランである。しかし燃料である以上、当然のことながら使えば減る。そこで約1年ごとの定期検査の時に順次取り換えている。問題はここで取り出した使用済みの燃料をどうするかである。使用済み燃料の中にはまだ利用できる有用な物質も含まれているので、それを抽出するということもありえる(これを再処理という)。それでもすべての部分が再利用できるわけでないため、いずれにしても捨てざるを得ない部分は出てくる。つまり捨て場所を確保しなければならない。
捨てるといっても簡単な話ではない。高レベル放射性廃棄物と呼ばれる極めて強い放射性物質だからである。再処理した場合でいうと、廃棄物は液体なのでそのままにしておくのは危険である。そこでまずはガラスで固める。ちょうどステンドグラスの中の染料が何百年も色落ちせずに、外に漏れ出さないのと同じ状態にするわけである。そしてガラスで固めた放射性物質はキャニスターと呼ばれる高さ1.3mくらいのステンレス製の容器に入れて廃棄することになっている。
◆決まらない捨て場所
問題はこの捨て場所である。キャニスターの表面近くにいると約20秒で致死量の放射線を浴びるため、とても普通に捨てるわけにはいかない。結局、地下深くに埋めて隔離することまでは決まっている。2000年に成立した「特定放射性廃棄物最終処分法」では深さ300mよりも深いところに埋めることを定めている。
ところが肝心のどこに埋めるかが決まっていないのである。近い将来に決まる見込みもまったくついていない。普通のゴミ処理場でも建設反対運動があるのだから、放射性廃棄物となれば当然だろう。この最後の行き場にまったく目途がついていないという点こそ原発の最大の泣き所である。このことはちょうど「トイレなきマンション」のようなものだと指摘されている。安全に操業していても必ず出てくるにもかかわらず、その捨て場が決まっていないのだから言い得て妙である。
しかも廃棄物の危険は極めて長期にわたって続く。代表的な放射性物質であるプルトニウムの半減期は2万4千年である。子や孫の世代どころか何百世代後の人たちにまでツケを残すわけである。野田政権は「子どもたちにツケを残さない」といって消費税増税を企図している。しかしその一方で放射性廃棄物というツケを残すことへの反省はないようである。
実は“捨て場所探し”は仮に原発をいますぐ全廃したとしてもやらなければならないことではある。日本で原発が稼働し始めてから今年で46年である。その間に溜まってきた放射性廃棄物があるからである。今はこの分は捨て場が決まらないまま溜めている状態である(放射性廃棄物は発熱するため埋める前に数十年は冷ます期間が必要だという面もあるが)。
再稼働するということはこの核のゴミをさらに増やすということと同義である。しかし原発事故から1年余り、この処理については何の前進もない。この問題に何の目途もつけないまま「電気が足りないので再稼働させてください」というのはいかにも拙速ではないだろうか。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月