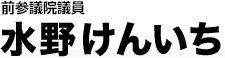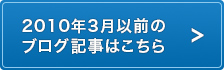- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
日曜討論に出演
2010.10.09
事務局より皆様へ
明日10日(日)のNHK「日曜討論」(午前9時より生放送)にみんなの党を代表して水野けんいちが出演いたします。
お時間ございましたら何卒ご視聴下さい。
明日午前11時頃より本会議にて質疑
2010.10.07
事務局より皆様へ
明日11時頃より、参議院本会議にてみんなの党参議院代表として、水野けんいちが20分間質疑をさせていただきますので、お時間ございましたらぜひご視聴下さい。
中間選挙
2010.06.23
うるう年に行なわれるのが米国大統領選と夏のオリンピックです。いずれも4年に一回です。
米国ではその4年の中間年に上下両院の議員選挙(上院は3分の1のみ改選)があります。中間に行なわれるので、これは「中間選挙」と呼ばれています。
オバマ大統領が当選したのが2008年。ですから次の大統領選は2012年です。そしてその中間年の2010年(つまり今年)秋にこの中間選挙があります。
中間選挙はトップリーダーである大統領を決めるわけではありません。ただ現政権への国民の中間的な審判を下すという点で大きな意味を持っているとされます。
日本に当てはめると衆議院選が政権選択の選挙だとすれば、参議院選がこの中間選挙に近いといえるでしょう。つまり政権に対する中間評価という位置づけです。
この中間評価で、今の民主党政権に合格点を与えて良いのでしょうか。良いわけはありません。そんなことをすれば、多くのマニフェスト違反が正当化されてしまいます。今後の政治家が「選挙の時だけ甘いことを言って後で反故にすればよい」などと考えるようになったら民主主義は崩れてしまいます。
また政治とカネの問題でも説明責任を果たさないまま「みそぎは済んだ」と正当化するようになるでしょう。
それに合格点=過半数をとれば、衆参両院を制することになりますから、暴走してもチェックすることさえできなくなります。
かといって自民党が勝てばよいというわけでもありません。昔ながらの族議員が息を吹き返してしまいます。
ですから私たち「みんなの党」がしっかりと頑張っていきます。御理解・御声援のほどよろしくお願い申し上げます。
絶滅危惧種
2010.06.23
今年日本で開かれる大規模な国際会議に「生物多様性条約 第10回締約国会議」があります。10月に名古屋市で行なわれるこの会議はCOP10とも呼ばれます。
現在全世界で確認されている種の数は175万種。未確認のものを含めるとその数倍から10倍以上とも言われます。
ちなみに現在生息している人類はすべてホモ・サピエンスという一つの種に属します。絶滅したネアンデルタール人はホモ・ネアンデルターレンシスという別の種になります。
犬はブルドッグもセントバーナードも一つの種に属します。一方、サルはチンパンジーとニホンザルはそれぞれ別々の種に分類されます。
こうした数多くの種の中には絶滅に瀕しているものも多くあるので、生物多様性を保全していこうというのが名古屋での会議の目的です。
絶滅危惧種のリストをレッドリストと言います。日本国内の絶滅危惧種については環境省がレッドリストを作成しています。
絶滅危惧と一口にいっても程度によっていくつかに分類されています。絶滅の危険が高い方から、
①絶滅
②野生絶滅
③絶滅危惧ⅠA類
④絶滅危惧ⅠB類
⑤絶滅危惧Ⅱ類
⑥準絶滅危惧
となっています。
具体的な動物でいえば、
ニホンオオカミ ・・・絶滅
トキ ・・・・野生絶滅
イリオモテヤマネコ・・絶滅危惧ⅠA類
そして数年前にはメダカが絶滅危惧Ⅱ類に指定されたということが話題になりました。
さて政治家にも絶滅危惧種がいます。というよりも絶滅してほしいタイプの政治家が多いかもしれません。
以下のような政治家は絶滅を歓迎したいところです。
・政策立案にたずさわらずひたすら役職だけを欲しがるような政治家
・利権あさりをする政治家
・選挙の時だけ甘いことを言って、後で責任は取らない政治家
・自分以外を虫けらのように思っている政治家
等々です。
ネット選挙解禁されず
2010.06.23
7月の参議院選挙で期待されていたことが「ネット選挙解禁」でした。
公職選挙法では選挙期間中に使える葉書やチラシの枚数に制限があります。これらの限定されたものだけが選挙期間中に“使える道具”というわけです。逆に言えば、それ以外は使っては駄目ということになります。
公職選挙法は昭和25年に制定された法律ですから、当然インターネットなどは想定していません。ですから“使える道具”の中にインターネットは入っていません。
そのため日々更新しているブログなども選挙期間中だけは「更新禁止」と解釈されていました。それはあまりにもおかしいということで、公職選挙法を改正して、今年の参議院選挙からはブログの更新などネット選挙を解禁する方向で与野党が合意していました。
ところが合意したにもかかわらず、公職選挙法は改正されませんでした。何故でしょうか。鳩山首相の突然の退陣劇の余波です。
内閣が総辞職すれば、新首相の選出や、所信表明演説などを行なわなければなりません。そのことに時間がとられて、公職選挙法改正どころではなくなってしまったのです。
まして支持率の回復に気を良くした民主党が、すぐにでも選挙戦に突入したくなり、早々に国会を閉じたこともあります。
党利党略のために必要な法改正が犠牲になったことは返す返すも残念です。まして解禁することには与野党とも異論はなかったわけですから、なおさらです。
では私に影響はあるかって?それは分かりません。ただちょっとした誤算ではありました。ネット選挙が解禁されることを見越して、ある程度の予定稿は書いていたからです(これは企業秘密でしたが・・)。
ネット選挙が解禁されれば選挙戦に突入しても、ブログの更新ができます。そうなれば投票日の7月11日(25日説も有力でした)までブログを書き続けられるわけです。
とはいえ選挙中は忙しくなるので、なかなか書く時間が取れないかもしれません。もちろん「○○駅で演説したらチラシを取ってくれる人が多くて嬉しかった」くらいのことは書けるでしょうが、それでは小学生の日記みたいです。
有権者に伝えるに値するブログにするには、ある程度の準備も必要です。ですから時間のある時に、一定の予定稿は書いておきました。
もちろん状況に色々な変化はありえるので、予定稿をそのまま掲載するわけではないにせよ、一から書くよりはかなり楽になりますから。
ところが6月24日以降は、書き溜めておいた予定稿は使えなくなったわけです。仕方なく最近はそれを放出しています。
ここ数日、普段よりもブログ更新が多めになっている大きな理由はそれです(企業秘密をバラしちゃいました・・)。
ネット選挙解禁は有権者への情報提供の機会が増えるわけですから基本的に良いことです。だからこそ各党とも賛成していたはずです。こうした必要な法律が党利党略で成立しなかったことはまったく残念なことです。
(つまり、このブログの更新は投票日まで凍結する予定でおります。申し訳ございません。)
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月