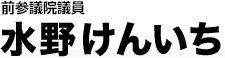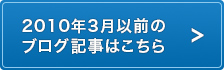- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
平均1年半
2010.06.22
G8サミット参加国に関するクイズです。アメリカ4人、フランス3人、イギリス5人、イタリア7人、日本14人という数字は何でしょう。
答えはこの20年間(1990年6月以降)の最高指導者の数です。
注)イタリアではベルルスコーニ首相やプロ―ディ首相などが退陣してから返り咲くことを繰り返しているので、こうした場合を複数にカウントすると延べ人数は11人となる。
確かに日本の首相はころころ変わります。20年で14人ですから平均1年半にも達しません。この間小泉首相が5年半つとめたので、それを除けば平均はさらに短くなってしまいます。
北朝鮮を見ると建国60年で最高指導者は金日成・金正日の2人だけですから、長ければ長いほど良いとは思いませんが、日本の場合いかに何でも変わりすぎだと思います。
だからといって菅政権に長く続いてほしいというわけではありません。最初に選挙目当てのバラマキをしておいて、そのツケを消費税増税で回収するなどということを公言する総理大臣には退陣を求めざるをえません。
くるくる首相が変わることを憂いつつ、「それでも今の首相を早く変えなきゃ」と思わざるをえない政権ばかりが続くのには困ったものですが・・。
CO2排出全国一
2010.06.22
千葉県にはいろいろな日本一があります。落花生の産出額は47都道府県で圧倒的な1位ですし、醤油の生産量もトップです。
変わったところでは「その県で一番高い山が全国一低い県」というのも千葉県です。県内で一番高い山は南房総市の愛宕山ですが、標高わずか408m。
東京都ならば奥多摩の雲取山(2017m)、神奈川県ならば丹沢山地の蛭ヶ岳(1673m)という具合にどの都道府県にももっと高い山があります。その中で408mの山しかない千葉県は「最高峰が一番低い県」という妙な勲章も持っているわけです。
またCO2排出量が全国一多いのも千葉県です。地球温暖化の元凶であるCO2の排出が1位というのはあまりありがたくない称号です。
CO2は家庭からも排出されますが、圧倒的に大きな排出源は製鉄所や火力発電所です。千葉県が1位になっているのは京葉工業地帯にその両方を持っているためです。2位は愛知県、3位は広島県ですが、逆にオフィスは多くても大規模工場の少ない東京都などは14位にとどまっています。
千葉県が1位なのは逆にいえばそれだけ工業が盛んだということで一概に悪いとは言えませんが、少なくとも排出量1位の県に住む人間としてこの地球温暖化問題にはより関心を払っていく責任はあると考えています。
投票率(その2)
2010.06.22
参議院選挙はこれまで21回行なわれています(補欠選挙は除く)。
その中で、投票率のベスト3は、
①1980年 75.5%(衆議院との同日選)
②1974年 73.2%
③1950年 72.2%
逆に、一番低かったのは1995年の44.5%です。ここ4回は連続して、50%台後半が続いています。
「投票率は体温に似ている」という説があります。体が危機に瀕すると体温が上がるように、国や社会が危機に陥ると投票率も上昇するというわけです。
そうした考えからすると、あまり高すぎない平熱くらいの方が、世の中が安泰の証拠といえるのかもしれません。
この説によると、低すぎるのも問題ということになります。体温が低くなりすぎると体に悪影響があるように、投票率も低すぎると民主主義が機能しなくなるというわけです。
昨今は「民主党には幻滅、しかし自民党にも戻したくない」という機運が非常に強くなっています。このままだとどちらも嫌だといって、投票率が大きく下落する懸念があります。
日本が「低体温症」に陥らないためにも第三極の「みんなの党」がしっかりとしなければいけません。
投票率(その1)
2010.06.21
投票率は選挙結果に大きな影響を与えます。
衆議院選挙だと一選挙区平均の有権者数はだいたい35万人くらいです。投票率が10%違うということは、3万5千人が投票所に足を運ぶか運ばないか、ということになります。
1万票以内の差で勝負が決まることも多いわけですから、3万5千人が投票するかどうかは勝敗を分ける極めて大きな要素です。
注)千葉県内における衆議院選の僅差の例
1996年 千葉4区 105票差
2003年 千葉3区 917票差
2006年 千葉7区補選 955票差
注)2003年に917票差で敗れた候補は比例復活当選した。
それだけに追い風を受けている政党は投票率が上がるのを望みます。
逆に堅い固定票をもっている政党は投票率が下がることを望む傾向にあります。どんなに投票率が下がっても自分たちだけは確実に投票に行けば、相対的に有利になるからです。
2000年の総選挙の直前に森喜朗首相が「無党派層は寝ててくれれば」と発言し、批判を浴びましたが、不人気だった森首相の本音が出たというところでしょう。
正直といえば正直ですが、言ってよい本音とよくない本音があります。
「多くの人が投票に行かない方が自党に有利」ということなどは、責任ある立場の人が言うべきことではありません。少なくとも矜持のある人ならば言えないせりふです。
さて「みんなの党」の支持率が上昇(直近だけ見ると少し違うかもしれませんが・・)しているから言うわけではありませんが、私としては、参議院選挙の投票率が高くなることを望んでいます。
有利・不利ということを考えないといえば、嘘になりますが、やはり、なるべく多くの人に投票に行っていただき、その中で審判を受けて勝利を掴み取りたいというのが立候補予定者としての偽らざる気持ちです。
(次号、“投票率〔その2〕”に続きます)
国会中継
2010.06.21
衆議院議員だった時に選挙区の支援者宅を訪れると、ちょうどテレビの国会中継を見ている(もしくは農作業中にラジオで聞いていた)ところだったということが何度もありました。
別に国会をさぼって選挙区にいたわけではありません。中継するのは普通は予算委員会なので、予算委員ではなかった私は自分の所属する委員会が開かれていなかったのです。
(テレビ中継が入る予算委員会は全閣僚が出席するため同時刻に他の委員会は開けません)
こちらは挨拶回り中で、相手は国会中継を見ているわけですから当然、その日の国会の状況については相手の方が詳しいわけです。
「総理もこんな答弁をしているようじゃ駄目だねえ」とか言われても、私はそれを見ていないのでよく分からないとなります。
日曜日の朝には政治報道番組が多くありますが、同じことが起こります。この時間帯には地元の行事が入りがち(例えばスポーツ行事の開会式など)なので、意外にこうした番組は見逃しがちになります。ここでもまた誰が何を言っているということはテレビを見ていた有権者の方が詳しくなります。
今は一人一人の有権者が多くの情報を持っている時代です。そして情報を集めようとすればやりやすくなってきました。テレビだけでなくインターネットで一次情報を手に入れることも可能です。国会のインターネット中継のアクセス数も昨年は衆議院で378万件と前年の1.5倍になり過去最高を記録したそうです。
それだけに投票行動も自分の頭で判断する人が多くなるのは当然です。そんな時代に組織固めだけに力を入れる政党は駄目だと思うのですが、どうやら二大政党ともそこから抜け出していないようで・・。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月