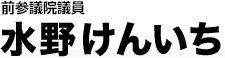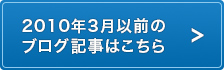- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
総裁選では麻生太郎氏に投票
2007.09.23
「総裁選では麻生太郎氏に投票」
自民党総裁選挙が行なわれ福田康夫氏が330票を獲得し、197票の麻生太郎氏を破って第22代総裁に就任することになった。ただ票数を見ると麻生氏の善戦という印象が強い。8派閥が雪崩を打って福田支持を打ち出した中で、麻生氏がこれだけの票を獲得したことは旧来の派閥政治への一撃となった点で喜ばしい。
さて私自身は今回の総裁選では麻生太郎氏に一票を投じた。私は無派閥議員なので派閥の締めつけなどとは無関係であり、自分の意思で決定した。麻生氏に投票した大きな理由は福田氏の政策のいくつかに違和感を覚えたためである。もちろん同じ自民党所属の議員なので共通する政策があるのも当然だが、それでも例えば対北朝鮮外交などの福田氏の姿勢には疑問を感じることが少なからずあった。端的に言えば北朝鮮に圧力をかけることに躊躇するような態度は疑問である。
また総裁選開始直後に党本部で行なわれた立会演説会での福田氏の演説もいただけなかった。高邁な理念・哲学を語るわけでもなく、かといって具体的な施策を述べるわけでもなかった。打ち出した具体的政策が「二百年住宅」だけだったというのは一国の総理を目指す人としては余りにも寂しいものだった。
こう書くと消去法で麻生氏に決めたように聞こえるかもしれないが、それだけではない。麻生氏の識見能力が総理総裁としてふさわしいと思った上で一票を投じたのも当然のことである。 とはいえ新総裁は決定した。大切なのは、今後自民党が国民の信頼を取り戻すことである。そして野党の主張のうち傾聴すべきことには謙虚に耳は傾けつつも無責任な政策は徹底して論破していくことである。私自身もそのために全力を尽くしていくことをお誓いしたい。
温暖化防止の具体策を提言
2007.09.01
「温暖化防止の具体策を提言」
〜早急なフロン規制が必要〜
地球温暖化をどう防ぐかが大きな課題になっています。今年の夏は国内で史上最高の40.9℃を記録するなど温暖化の進行はいよいよ明らかになってきました。このままでは海面上昇はもちろんのこと、台風被害、マラリアなど感染症の増加、食糧危機の到来などが懸念されています。ではこれを食い止めるために何が必要でしょうか。省エネ機器の普及や自然エネルギーの活用など様々な施策が求められていますが、これらに加えた具体策として私はフロンの規制を提言しています。
フロンガスは20年ほど前、オゾン層を破壊するとして問題になりました。そこでオゾン層を破壊するタイプのものはすでに生産が規制されています。しかしオゾン層は壊さないが温暖化を引き起こす新タイプのフロン(HFCと呼ばれる)の生産には何の規制もなく年々増産されているのです。地球温暖化を引き起こすガスとしては二酸化炭素やメタンが有名ですが、HFCの温室効果は二酸化炭素の120〜15000倍と極めて強力なものです。しかもフロンが他のガスと決定的に違うのは自然界に存在しない人工物質だという点です。つまりこれだけ地球温暖化の危機が叫ばれ、多くの人が省エネ努力などをしている時に、フロンメーカーはわざわざ強力な温室効果ガスを人為的に製造販売して利益を上げているわけです。こうしたことは倫理的にも看過できません。
地球温暖化問題は病気と同じで早め早めの対策が必要です。遅くなってから対策をとっても手遅れになる危険性があります。そのためにもフロンについては生産を禁止するか重税を課して価格競争力を失わせるなどの手法を早急にとる必要があると思います。
地球温暖化防止のために
2007.05.01
「地球温暖化防止のために」
地球温暖化という危機が深刻化しています。このまま放置しておけば今世紀末には最大6.4℃の上昇が見込まれています。1℃上昇すると水不足で苦しむ人が5000万人が増え、マラリアによる死者が30万人増加するという試算もあります。また経済面でも温暖化の進行は世界のGDPを5~20%も押し下げると危惧されています(注)。 温暖化の主原因は大気中の二酸化炭素濃度の上昇です。二酸化炭素は石油・石炭など化石燃料を燃やした時に排出されます。人類が化石燃料をほとんど利用しなかった産業革命以前(つまり1750年以前)の二酸化炭素はだいたい280ppmでしたが、年々上昇して現在は380ppmとなっています。
これを食い止めるためには二酸化炭素の排出を削減することが必要です。そこで安倍首相は2050年までに排出量を半減することを提唱しました。これまで政府がこうした長期目標を掲げてこなかったことに比べて大きな前進といえます。また国際社会への働きかけも重要です。ただ各国に訴えかけるといっても日本自身がしっかりと削減を成し遂げていなければ説得力に欠けてしまいます。とりわけ京都議定書で日本が国際約束した90年比6%削減の達成は喫緊の課題ですが、残念ながら現実の国内排出量は削減どころか7.8%も増えてしまっています。まずはこれを何とかしなければなりません。もちろん国民一人一人の省エネ努力も大切です。同時に二酸化炭素の排出割合を企業:家庭でみると79:21で企業が多いことを考えると、大口発生源である産業界により積極的な取り組みを求めていくことが必要と考えます。
注)数字についてはIPCC第4次評価報告書や英政府が委託研究した結果の「スターン・レビュー」などを引用
その他、グラフとして
大気の成分
窒素 78.09%
酸素 21.95%
アルゴン 0.93%
二酸化炭素 0.04%
0.04%とは400ppmのこと
拉致問題を風化させるな
2007.05.01
「拉致問題を風化させるな」
「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化なし」というのが安倍内閣の方針です。国交正常化というのは北朝鮮への多額の経済協力を意味します。1965年に韓国と国交樹立をした時には有償2億ドル、無償3億ドル、合計5億ドルの経済支援をしています。貨幣価値の変化などを勘案すれば、北朝鮮側が日本円で1兆円を超える援助を期待していることは間違いないところです。拉致問題が解決しないまま莫大な経済協力だけを進めるわけにはいきません。ましてその支援が日本に向けた核開発やミサイル開発につながりかねないのですからなおさらです。
政府は拉致問題の解決として①すべての生存者の帰国、②真相の究明、③容疑者の引渡し、の3点を掲げています。まず①の生存者の帰国は当然のことです。ごく普通の生活をしていた人たちが突然さらわれて海のかなたに連れて行かれたのですから「返せ」というのは当然すぎるほど当然の要求です。②の真相究明も現状ではまったく進んでいません。北朝鮮が出してきた「遺骨」と称するものをDNA鑑定したら偽物だと判明したことなどは何をかいわんやです。そして拉致に携わった工作員・辛(シン)光(ガン)洙(ス)が北朝鮮国内で英雄として扱われている現状も容認することはできません。③の引渡しも強く求める必要があります。
拉致問題は日本にとっての重大な主権の侵害であると同時に極めて深刻な人権の侵害です。この問題を風化させずに一歩でも解決に近づけるよう今後も全力を尽くしていきたいと思っています。
温暖化防止情報開示訴訟について
2007.02.01
「温暖化防止情報開示訴訟について」
◆国の敗訴
1月30日、「温暖化防止情報開示訴訟」で大阪地裁は国の全面敗訴の判決を言い渡した。日本で初めての地球温暖化防止訴訟に司法の判断が下されたことになる。 判決に不服がある時は14日以内に上訴できる。つまり国が控訴するとなればその期限は2月13日となる。 国が関係する訴訟は法務省が一元的に扱う。法務省にはそのための機関・訟務部門がある。そして現在、私自身、法務省の副大臣という立場にある。私はこの件に関して控訴すべきではないと考えている。敗訴は敗訴としてきちんと認め、地球温暖化対策に真摯に取り組んでいく契機とすべきである。
◆温暖化防止情報開示訴訟とは
理由について述べる前に何が争われていたのかを簡潔に述べてみたい。経緯は温暖化防止に取り組むNPO「気候ネットワーク」が04年に経済産業省に対して情報開示を求めたことに始まる。省エネ法という法律によって一定規模以上の事業所はどのエネルギーをどれだけ使用したかを経済産業省に毎年報告することになっている。つまり○○発電所や△△製鉄所がどれだけの重油や石炭を消費したかという資料を経済産業省は保有している。本来、政府が持っている情報は国家機密や個人情報を除けば情報公開法によって請求があれば原則公開されることになっている。 そこで気候ネットワークは経済産業省の持っているこのデータの公表を求めた。エネルギーの使用量は温暖化の主原因である二酸化炭素の排出量に密接に関わるからである。温暖化対策を効果的に進めるためにもどのようなエネルギーがどこでどのくらい使われているかの現状を把握するのは重要である。ところが経済産業省は85%の企業(4280事業所)については数値を開示したが、残り15%分(753事業所)は不開示とした。
つまり黒塗りにして出してきた。これらの企業が「うちの数値は企業秘密であり公開されては困る」と言ったためである。これを不服とした気候ネットワークは開示を求めて国を相手に行政訴訟を起こした。そうなると先に述べた通り法務省が受けて立つ形になる。そして今回、大阪地裁は経済産業省の判断を不当として開示を求める判決を出したわけである。
◆私の関わり
私が控訴すべきでないと考えている背景には自分自身が法務副大臣就任以前からこの問題に関係し、一通りの経緯を知っていることがある。その中でどう考えても経済産業省の主張が正しいとは思えない。実は私も02年に経済産業省に対して同様の情報開示請求を行なったことがある。気候ネットワークが請求する2年前である。この時も同省は一部企業のデータは不開示にした。開示部分を解析した結果は05年の温暖化対策推進法の改正につながったと考えているが、すべ てが開示されていればより良かったとの思いはぬぐえない。私自身は裁判という選択肢はとらなかった。 だが経済産業省に対しデータを全面開示すべきだという思いを強く持ったのも正直なところである(私の情報公開請求の経緯は本ホームページに掲載した『経済産業省への挑戦状〔上〕〔中〕〔下〕〔完結編〕』『解説・温暖化対策推進法の改正について』をご参照いただきたい)。
◆本当に企業秘密なのか
裁判で争われたのはデータが企業秘密にあたるかどうかである。情報公開法第5条は「当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」の場合には不開示にすることを認めている。 経済産業省はこれに該当する企業秘密なので不開示にしたという。しかし85%の企業は最初から公表してかまわないという姿勢をとっている以上、あまり説得力があるとは思えない。 もちろん業種などによっては本当に秘密にしたいという場合もあるかもしれない。だがその主張は「二回」にわたって判決で退けられている。この点を重く見る必要があるだろう。実は今回の判決は「二回目」なのである。昨年9月に名古屋地裁でもやはり気候ネットワークが経済産業省を相手取った訴訟の判決が下りている。訴えの内容も結果も今回とまったく同様だった。開示されれば当該企業にとって本当に損害があるのかどうかも疑わしい。決定的な企業秘密というほどの ものかも怪しいのである。裁判の進行中に開示に応じた企業が続出したことがそれを裏付けている。裁判中に開示したというのはどういうことなのか。つまり開示請求を受けた当初は「うちのデータを公表されては困りますよ」と経済産業省に言っていた会社が、いざ裁判にまでなってみると「裁判に巻き込まれるくらいなら開示しよう」という姿勢に転じたということである。企業の態度が変われば経済産業省が不開示を続ける理由はない。そこで開示率は92%にまで上昇した。 これ自体は歓迎すべきことである。ただ逆に言えば実はそれほど決定的な企業秘密でもなかったことの証しでもある。「企業秘密なので開示できません」という業界の言い分をそのまま繰り返していた経済産業省の当初の姿勢も問われよう。
開示が嫌だという会社側の気持ちも心情的には分からないではない。政界を例にとれば、政治資金の収支報告書の内容を公表されるというのはあまり気持ちのよいものではないというのが大方の政治家の本音だろう。それでも公開が必要なのは、政治資金の流れを国民の眼で監視してもらうことが政治倫理の向上という公益につながるからである。エネルギー情報も同じである。開示して多くの人の眼に触れることによって各社の省エネ意識もより高まるはずである。せっかく企業にエネルギー使用状況を報告させていても、現状のように経済産業省だけが情報を抱え込んでいるのでは一体何の役に立っているかという疑問の方が先に立つ。
なお仮に企業秘密だったとしても絶対に非公開にしなければならないというわけでもない。情報公開法第7条は公益上特に必要があると認められるときには、そうした場合でも開示できる規定になっていることを付記しておく。
◆結び
いま地球温暖化対策は急務の一つである。先日IPCCの第4次評価報告書がまとまり、今世紀の百年間で地球の平均気温は最悪で6.4℃上昇するとの予測が示された。こうした温暖化を防止するために京都議定書が締結され、日本は6%の温室効果ガスの排出削減を約束した。ところが実際の排出量は削減どころか増加している。このままではいけないと誰もが感じている。だからこそ新たな対策が必要だということで政府は京都議定書目標達成計画の見直しを進めている。 有効な対策をとるためには現状がどのようになっているのかの基礎データが必要である。そのためにも政府が持っているエネルギー使用情報は最大限公開に努めるべきだろう。
経済産業省は控訴を求めている。私は控訴せずに一審で確定させてよいと考えている。現在、国が抱えている訴訟は約1万2千に上る。そして今回の例に見るように国が敗訴することも多くなっている。何も私は国が負けることを喜ぶわけではない。そのような国家性悪説に立つつもりもない。だが中には負けるべくして負けているものもあるだろう。そうした裁判を他省庁から頼まれたからといって法務省が必ず引き受けるというのも妙なことだと思っている。
1万2千の訴訟に対し法務省訟務部門の定員は394名で人手不足が悩みの種である。そのため現在国会で審議中の来年度予算案では7人の純増が盛り込まれた。公務員削減の流れの中で増員が認められたのはそれだけ訟務の体制強化が重要だからである。同時に限られた人手を有効に使う必要性もある。争うに値しない問題は潔く敗北を認めて、争う価値のある問題に有為な人材を回すことも大切ではないだろうか。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月