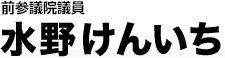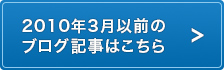- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
解説・温暖化対策推進法の改正について
2005.06.11
解説・温暖化対策推進法の改正について
~経済産業省や経団連の抵抗を押し切った法改正。水野賢一の5年越しの主張がついに結実~
◆温暖化対策推進法の改正案が成立
地球温暖化対策推進法の改正案が成立した。衆参両院ともに全会一致での可決だった。この法律は1998年に制定され、2002年に改正されているので今回が2度目の改正となる。 今回の法改正の根幹は事業所ごとに温室効果ガスの排出量を算定・報告・公表する制度の導入である。どの工場がどれだけの二酸化炭素(CO2)を排出したかを明らかにすることを義務づけたともいえる。 法的な義務の有無に関わらず、温室効果ガスの排出量を自主的に公表している例は多くある。
環境への意識の高い企業は環境報告書を作成し、自社の二酸化炭素排出量などを公にしている。だが一方で公表に後ろ向きな事業者が多いのも事実である。環境省が03年度に行なったアンケート調査によると回答した2795社のうち二酸化炭素の排出量を公表していたのは721社にとどまっていた。約26%である。調査対象となったのは6354社なので未回答も多い。
こうした調査では、自社の環境対策に自信を持っている企業ほど回答する傾向がある。それを勘案すると未回答分を含めた全体での公表率はかなり低めのものになるだろう。やはり自主的な取り組みだけに任せておいては不十分なのである。 法律で明確な義務にする必要がある。それが今回の改正の趣旨といえる。せめて一定量以上を排出している企業の場合は、その数値を公開するようにしたわけである。
こうした公表制度を創設することは私にとって年来の主張だった。実は02年の改正時にもそのことを強く訴えたが、当時はまだ反対論が強く、残念ながら改正案に自説を盛り込むには至らなかった。その頃、反対の中核となっていた経済産業省と応酬を繰り返したことも懐かしい思い出である(その経緯は本ホームページの『経済産業省への挑戦状〔上〕〔中〕〔下〕〔完結編〕』を参照いただきたい)。それから3年を経て、現在、私は自民党の環境部会長の任にある。
就任してからは、最重要の課題として持論である本法案に取り組んできた。その過程では産業界や経済産業省が再び抵抗し、内閣法制局まで難色を示した。それらを乗り越えて在任中にこの制度が新設できたことは感慨深い。本稿ではこの改正温暖化対策推進法の内容を概観し解説してみたい。
◆公表制度導入の意義
内容に立ち入る前に、まずこうした制度がなぜ必要なのかを考えてみたい。排出量を公表したからといって直接的に削減を約束するものではない。それでもこの制度にはいくつかの意味がある。まず情報公開という面である。透明性が求められている現在、環境情報も積極的に開示してもらう必要がある。そしてそのことは企業の環境意識を高めることにもつながる。自らの排出量を算定すれば野放図な排出を慎むようになるだろう。また外部の目を気にして無責任な放出にも歯止めがかかるはずである。トルエン・キシレン・ベンゼンなどの化学物質についてはPRTR法という公表制度がすでに存在するが、この法律が施行されると初年度に比べ2年目の届出排出量は7.1%も減少した。
さらに今後の温暖化対策の重要な施策と考えられているキャップ&トレード方式の国内排出量取引に道を開くことにもなる。排出量取引といっても現在どれだけの温室効果ガスを排出しているのかが分からなければ成り立ちえない。
もちろんキャップ&トレードを導入するかどうかは今後大いに議論しなければならない。だが少なくともその前提となる公表制度を今のうちに整えておくことには意味がある。
だからこそ同様の制度は諸外国でもすでに実施されている。EUでは昨年2月からデータの公開が始まっており、イギリスはそれに先立ち98年に導入している。またカナダでも昨年3月に法制化された。国内でも自治体レベルでは導入が進んでいる。排出量の公表などを条例で義務づけている地方公共団体は04年10月現在で 9都県・3政令指定都市の合計12自治体となっている。
先に述べたように国レベルでも温室効果ガス以外の物質についてはこうした公表制度は存在している。99年に成立したPRTR法によって各企業はトルエンなど354種類の化学物質については排出量を公表する義務を負っている。ところが不思議なことに二酸化炭素などの温室効果ガスについてだけは制度が存在しなかった。それだけに今回、温室効果ガスも公表を制度化することはごく自然なことであり、むしろ遅きに失した感さえある。
◆対象となる事業所
改正法の内容をもう少し詳しく見てみよう。
まず温室効果ガスを一定以上排出している者は自らの排出量を算定し、それを国に報告することが義務となる。国は報告されたデータを集計・公表する。対象となる温室効果ガスは二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・HFC・PFC・SF6(六フッ化硫黄)の6つである。
さて温室効果ガスの排出量を報告させるといっても、出しているところすべてに義務をかけるというのは現実的ではない。二酸化炭素というのは車に乗っても電気を使っても排出される。つまり小さな町工場や民家などを含めあらゆるところから出ているのである。そのすべてに算定・報告の義務をかけるわけにもいかない。 そこで対象は一定以上温室効果ガスを排出している事業所に限ることにした。「裾切り」を設けたわけである。そうなると裾切りの値をどのくらいにするかが問題になってくる。これは法律には明記していない。今後政令で定めることになっているが、エネルギー起源の二酸化炭素の場合は、省エネ法の第一種・第二種のエネルギー管理指定工場とする予定である。これは電気・熱のエネルギーを年間に原油換算で1500kl以上消費する事業所を指す。原油換算1500klというのは二酸化炭素の排出量でみると概ね3000㌧前後になる。「概ね」と幅のある言い方になるのは電気を主に使う場合と熱を中心に使う場合で違いが出るためである。
他の5ガスは二酸化炭素換算で3000㌧以上排出していれば報告の義務がかかってくる。 例えばメタンは二酸化炭素よりも21倍の温室効果があるため、143㌧以上出していれば対象になる。また非エネルギー起源二酸化炭素も同じく3000㌧を裾切り値とした。なお報告はガスごとなので、二酸化炭素 8000㌧ メタン 100㌧(CO2換算で2100㌧) という場合には二酸化炭素の排出量だけを報告すればよい。
◆報告は事業所ごとに
この新制度は「事業者」ではなく「事業所」ごとに算定・報告することになっている。電力を例にとれば東京電力・関西電力という会社ごとではなく、発電所ごとの報告となる。データとしてはそれだけ詳細になる。対象となる事業所数は概ね以下のようになると見込まれている。
二酸化炭素 約16000 メタン 約20
一酸化二窒素 約250 約130 約10
PFC 約130 SF6 約150
二酸化炭素に関していえば、対象となる事業所が排出している量は全国の総排出量の54%になる。一見これは少なく見えるかもしれない。だが54%のカバー率というのは実はかなりの高率なのである。一軒一軒の家庭に報告義務を課せない以上、最初から80%とか90%にはなりえない値だからである。産業部門、つまり工場だけに限れば排出量の90%強をカバーできると試算されている。諸外国と比べても裾切り値は厳しい。二酸化炭素を比べてみるとEUが10万㌧、イギリスが1万㌧、カナダは10万㌧(ただしカナダは温室効果ガス排出量の合計のCO2換算)である。カバー率でもEUは42%にとどまっている。導入こそEUに遅れをとったが、より厳しい制度を作ることができたと考えている。
先に算定・報告は「事業所」単位だと述べた。工場の場合はそれで問題はない。ところが運送会社などは会社全体では大量の二酸化炭素を出しているが事業所ごとに見れば小規模だということが多い。それだと報告義務がかからないことになってしまう。運輸部門は事業所単位の報告になじみにくいのである。そこで運輸部門だけは例外として日本通運とかヤマト運輸など企業単位で報告を受けることにした。
一方、今回の新制度ではコンビニエンスストアやファーストフードなどチェーン展開している店はほとんど対象にならない。一店ごとに見れば小規模なので、普通は原油換算1500klのエネルギーは使わないからである。これも運輸部門と同じようにグループ全体として報告させるようにすべきかもしれない。今後の検討課題といえる。
◆企業秘密
算定・報告・公表制度に対しては産業界・経済産業省の反対が強かった。例えば経団連は昨年7月に中央環境審議会地球環境部会に出した意見書で「民間企業に情報開示を義務付ける法律や制度は不要である」と述べていた。彼らも公表そのものが悪いといっていたわけではない。だがそれは自主性にまかせるべきだと主張し、義務を制度化することには抵抗していた。反対論の論拠はいろいろあったが、中でも「排出量は企業秘密だ」という声が根強かった。これに対し私は企業秘密のはずがないと主張した。特許のようなものならばいざ知らず、どれだけの二酸化炭素を排出したかが秘密のはずがない。もしこれを企業秘密だと強弁するなら資本金も経常利益も従業員数も全部秘密だということになってしまう。ましてPRTR法で化学物質については報告義務がある中で、二酸化炭素だけは秘密だといっても通用するはずがない。
それでも法律の中では、公開することによって本当に正当な利益が害される場合には、一定の配慮をする規定を設けた。なぜそうした制度を盛り込んだのか。私自身は二酸化炭素排出量は企業秘密に当たらないと思っている。ただ温室効果ガスにはいろいろなものがある。例えば液晶や半導体を生産する時に反応ガスとしてSF6という特殊な温室効果ガスを使用する。この排出量はライバル会社に知られると深刻な事態になるという。そこで各社とも情報管理には細心の注意を払っている。しかも主な競争相手の韓国・中国企業は公表していない。そうした中、自分の手の内だけをさらけ出すと国際競争力上、大いに不利になるという。そこで法律では事業所管大臣が本当に必要だと判断した時は、公表の仕方を大くくりにすることを認めた。大くくりという時に二つの方法がありえる。一つは本来ガスごとに行なうべき公表を温室効果ガス全体で行なうことである。普通ならば二酸化炭素は5万㌧、SF6は2万㌧(CO2換算)と公表すべきところを、温室効果ガス全体で7万㌧ということも可にしたわけである。これならばSF6の量は全体の中にまぎれてしまうので秘密は保持できる。もう一つは事業所単位でなく、企業単位での公表にすることである。これによって工場ごとの排出量は全体にまぎれることになる。 例外的にこうした措置もありえるとはいえ、公表こそ原則であり、まったく開示しないなどということは許されない。また企業側が「これは秘密です」といったら自動的に秘密扱いになるわけではないのは当然のことである。その点は事業所管大臣がしっかりと判断をすることが求められる。
◆正しい報告を
さてこうした算定・報告・公表制度の大前提となるのは企業が正しい報告を行なうことである。でたらめな数値が報告されたならば公表制度は意味を持たなくなる。かといって報告がすべて正しいかどうかを国がチェックするというわけにもいかない。行政コストがかかりすぎるからである。法律は国に立入検査を行なう権限などは付与していない。代わりに報告を怠った場合や虚偽報告には罰則として20万円以下の過料が課されるようになっている。この部分はPRTR法を踏襲している。
こうした仕組みは正しい報告をするはずだという性善説に立っているともいえる。ところが最近、企業による虚偽報告が相次いでいる。環境情報もその例に漏れない。昨年11月には三井物産がディーゼル排ガスの除去装置であるDPFのデータを捏造していたことを認めた。今年2月にはJFEスチールが排水データを改竄していたことが発覚した。
日本を代表する有名企業までもが、このような不祥事を引き起こしたのである。今後、もし温室効果ガスの排出量に関しても改竄や虚偽報告が横行するようであれば制度の根幹を揺るがすことになりかねない。罰則の強化や立入検査権の創設なども検討せざるをえなくなる。そうしたことがないように、正確な報告が行なわれることを願いたい。
◆抑制から削減へ
今回の法改正ではそれ以外にもいくつかの細かな修正をしている。あまり注目されていないが、その一つを挙げておこう。従来の温暖化対策推進法は、温室効果ガスの「削減」という言葉を使わずに一貫して「抑制」という語を使っていた。「削減」と「抑制」には大きな違いがある。「削減」というのは文字通り減らすことだが、「抑制」というのは伸びを抑えるということである。増加そのものはやむをえないという響きがある。
この法律は京都議定書を達成するための国内担保法的な性格を持っている。97年の議定書採択を受けて、翌年に法律が制定され、02年の議定書批准と共に法律も改正されたという経緯もそれを裏付けている。京都議定書が日本に求めているのは温室効果ガスの6%削減である。担保されるべき議定書が「削減」と言っているのに国内担保法が「抑制」と言うのはいかにもおかしい。やはり法律でも「削減」という用語を使うのが筋だろう。もちろん法律の文言を変えたからといって劇的に排出量が減少するとは限らない。だがこれは姿勢・意気込みの問題なのである。政府が温暖化に真剣に取り組むというのならば「削減」を使うべきである。
そこで昨年10月にこの法律について議論をした自民党環境部会の席で、部会長として私から環境省側に「抑制の語を削減に変えることを検討するように」と指示を出した。そして今回の改正では何か所かは「抑制」の文言を「削減」に直すこととした。本来すべての「抑制」を「削減」に変えたいところだったが、残念ながらそれはかなわなかった。横槍を入れてきたのはお決まりの経済産業省・経団連ではなく、むしろ内閣法制局だった。単に意気込みを示すという理由だけで用語を変更するのはまかりならんという論理である。そこで政府・自治体が立てる計画の部分に限って「削減」に変更することで折り合った。せめて公共機関については率先垂範の姿勢を示すのは問題ないだろうということである。いずれにせよ大切なのは用語を変えることではなく、排出量を減らすことである。削減計画の策定を求められる政府・自治体はもちろんのこと、事業者なども削減に向けて全力を尽くすことを強く求めたい。
◆公表方法
温暖化対策推進法は改正された。改正部分が施行されるのは06年4月なので、その翌年度には06年度分の温室効果ガス排出量が公表されるようになる。公表は次のような形で行なわれる。各事業所から上げられてきた報告は国が集計し、都道府県別、業種別、企業別などの排出量として公表される。千葉県内の事業所からはどれだけの二酸化炭素が出されたとか、鉄鋼業界からは○○㌧ということが発表される。 企業別の公表についてはやや詳しく述べたい。ある企業が5つの対象工場を持っていれば、5つの報告が提出されることになる。それを国が合計した上で公表する。逆にいうと工場ごとのデータは国の方から積極的に公表をすることはない。請求があったときにのみ開示する。請求の仕方はいろいろある。特定の事業所の排出量データを開示するように求めることも可能だし、全国1万数千の対象事業所全体のデータを請求することも可能である。後者の場合は紙にすると膨大な量になるので、CD-Rで渡す形になりそうだ。これもPRTR法と同じである。ちなみにPRTR法では全国すべての事業所のデータが入ったCD-Rは1100円で購入できる。
企業別の公表は改善の余地があるように思われる。事業所ごとの報告をわざわざ国が企業単位に名寄せして合計値を出すわけである。そんな手間のかかることをせずに、事業所ごとの生データそのものをホームページなどで公開すればすむ話である。その方が行政コストもかからない。国民側からみても開示請求という面倒な手続きが不要になる。このあたりは公表制度が定着してきたら見直しても良い点だと思う。
◆結びに
ようやくのこと算定・報告・公表制度が創設された。これまでの経緯を思えばよくここまで来たとの感もある。ただ新制度の導入というのは目的ではない。むしろ手段である。肝心なのは実際に温室効果ガスの排出量を減らすことである。まずは京都議定書で約束した6%削減を達成することが必要である。だが京都議定書を達成しさえすれば事足れりということでもない。
最近の知見によれば温暖化を食い止めるには最終的に温室効果ガスの排出量を現在の4分の1くらいにまで下げる必要があるという。京都議定書は入り口にすぎない。現時点ではその京都議定書の達成も難しいと思われている。先日発表された03年度の温室効果ガスの排
出量は基準年の90年度に比べ8.3%増になってしまっている。減るどころかかえって増加しているのだ。
そうした中で、算定・報告・公表制度の実現というのは排出量削減に貢献することは間違いない。とはいえ地球温暖化を防止するという大目的の中では、ほんの小さな一歩である。その一歩を確実に実施することで、大きな前進・成功につながるようにしていきたい。
効果を上げたディーゼル条例
2004.10.01
「効果を上げたディーゼル条例」
条例施行から1年。大気環境保全と公害被害者救済のために必要なことは….
◆ディーゼル条例とは
首都圏でディーゼル条例が施行されて1年が経つ。昨年10月、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県でディーゼル条例が一斉に施行された。 これにより粒子状物質(PM)を大量に排出する旧式のディーゼルトラック・バスは、PM除去装置をつけなければ走行できなくなった。この動きを主導したのは石原都知事である。平成11年に就任した石原知事はすぐさまディーゼル車NO作戦を打ち出し、翌年にはディーゼル条例を制定した。 時を同じくして兵庫県尼崎市の公害訴訟で粒子状物質による健康被害が認定されたこともあり、対策を求める声は他県にも広がっていく。東京都に続いて千葉県、神奈川県、埼玉県も同様の条例を制定し、昨年の一斉施行に至った。
ディーゼル車の排気ガスはガソリン車よりもはるかに汚れている。排気ガスに含まれる主な有害物質として窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)があるが、いずれもディーゼル車の方が大量に排出する。条例が狙っているのはこのうちPM削減である。それまでPM対策が特に遅れていたからである。
例えば排ガス中のPM濃度の規制は平成6年まではまったくなかった。しかもトラックやバスは耐久年数が長いので昔の車がそのまま走っていることが多い。(財)自動車検査登録協会によると普通乗用車の平均使用年数が9.7年なのに対し普通トラックは12.8年、バスは15.8年である。未規制時代のトラックやバスが今なお使われていても別に不思議ではない。そこで条例では、こうした車はPM減少装置をつけなければ走行できないようにした。
PM減少装置としてはDPFや酸化触媒が実用化されている。走る限りはこうした装置の装着を義務づけたともいえる。 条例施行から1年経った今、大気汚染の指標を見ると明らかに改善に向かっている。東京都の自動車排出ガス測定局では平成15年度に浮遊粒子状物質(SPM)の年平均値が23年ぶりに0.04μg/m3を割り込んだ。千葉県でも昭和57年度の観測開始以降で最低の濃度を記録した。SPM濃度は気象状況などの影響も受けるので即断はできないにせよ、改善していることは間違いない。注目すべきなのは15年度といっても後半、つまり規制が始まった10月以降の改善が顕著だという点である。やはり条例は効果をあげているといえよう。
◆ディーゼル条例は緊急避難
ただ忘れてはならないのはディーゼル条例は自動車排ガス対策の抜本策ではないということである。むしろ一時しのぎの緊急対策といえる。そこで国はディーゼル車対策として別の手法をとっている。 自動車NOx・PM法である。この法律は平成13年に改正・強化された。ちょうど首都圏で相次いで条例が制定されている頃である。大雑把な分類をすれば、条例がディーゼル車にDPFなどを装着することを義務づけているのに対し、NOx・PM法は古いディーゼル車の買い替えを強制している。前者が短期的な緊急避難措置なのに対し、後者は中長期的に必要な施策といえる。
都が条例化を表明した時、国は冷やかな姿勢だった。当時の環境庁は「都が条例を制定することにあえて反対はしないが、国が進めている自動車NOx・PM法の方が効果がある」という態度だった。 その背景としては、一つには石原知事が繰り返し口にした「国の対応が鈍いから都が独自にやる」といういわゆる慎太郎節への反発もあっただろう。都に先を越されたという思いもあったかもしれない。 だがそうした負け惜しみとばかりはいえない。実際にディーゼル条例よりもNOx・PM法の方が厳しく抜本的な対策になっている面も多い。条例はPMだけを取り締まり対象にしているが、法律はその名の通りNOxとPMの両方を対象にしているためである。 古いトラックにDPFを付けたとしよう。そうすれば確かにPMは低減する。だが旧型車は同時に大量のNOxも排出する。ところが条例が問題にしているのはPMだけなので、この車の走行を止めることはできない。他方、自動車NOx・PM法ならばこうした車の登録も禁止できる。しかもPMの規制値だけを比べても法律の方が厳しいのである。また条例ではディーゼル乗用車に規制がかからないのに対し、法律はこれも対象にしている。
だからといってディーゼル条例が無意味だというわけではない。緊急対策として十分その意義は大きかった。とりわけPMの被害に光を当てた効果は絶大である。緊急対策と恒久対策は両方そろって効果がある。政府は自動車NOx・PM法に基づく基本方針で平成22年度までに浮遊粒子状物質の環境基準を概ね達成するという目標を掲げている。この目標に向けて今後の対策が着実に効果をあげていくことが期待されている。
◆軽油について
ディーゼル条例と自動車NOx・PM法が相互補完的なものだということはすでに述べた。だがそれだけあれば十分というわけではない。他にもやるべきことはある。不正軽油の撲滅も重要な課題である。 ディーゼル車の燃料は軽油である。しかしディーゼルエンジンは適応力に優れ、正規の軽油以外(例えば灯油と重油を混和したもの)を入れても走りうる。 走るには走るがやはり正規の燃料でないために黒煙を撒き散らすことになる。 今年6月の地方税法改正で不正軽油製造の罰則は5年以下の懲役または500万円以下に引き上げられた(従来は1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。さらに法人の場合は3億円までの重課もある。こうした新法を駆使しての徹底取り締まりが必要である。 規制や取り締まりだけでなく、脱ディーゼル化へと経済的に誘導することも考えてよい。軽油とガソリンの税率の格差解消はその一つである。ディーゼル車が普及した背景には、軽油の価格がガソリンよりも安いことがある。なぜ安いのか。かかってくる税率が低いためである。1リットルあたりにかかる税金を比べるとガソリンが53.8円、軽油が32.1円となっている。軽油の方が実に22円も安い。 これだとディーゼル車の方が経済的に特だということになる。国が政策的にディーゼル車を優遇しているといわれても仕方ない。これも見直すべき時である。
◆自動車メーカーの責任
自動車会社の責任についても触れておきたい。 メーカーには社会的責任がある。まず排ガスがきれいな車を開発するという責任がある。この点はかなりの進展が見られる。大型ディーゼル車のPM排出規制は平成6年に始まるが、来年度から始まる規制値では平成6年当時に比べて25分の1以下に排出量を抑えなければならない。これに適合する車も今秋にも登場すると見込まれる。低排出ガス車の開発は著しい。乗用車でもハイブリッド車・天然ガス車など低公害車が続々と出てきている。
だがメーカーにはもう一つの責任がある。過去に大気汚染物質を大量に排出する車を販売しつづけた責任である。訴訟でこれが問われたことがある。 平成14年に一審判決が出た東京大気汚染訴訟である。判決はメーカーの責任を認めなかった。しかしそれでよいのだろうか。走れば必ず有害物質を撒き散らす商品を生産・販売して本当に責任がないのだろうか。しかもそれによって利益を上げているのだ。 工場排煙をめぐる公害訴訟では企業が多額の賠償金や和解金を原告住民に支払っている。例えば尼崎公害訴訟では自動車排ガスと工場排煙の双方が問題になった。工場排煙に関しては、煙を出した9社は和解金として合計24億円余りを支払っている。だが自動車メーカーの負担はない。おかしなことである。
まして昨今の排ガス対策はメーカー側からすると儲ける好機となっている。排ガス規制で旧式の車に乗れなくなれば、最新規制適合車に買い換えざるを得なくなる。いわば特需が起こった。自分で大気汚染の原因を作っておきながら、それを基に特需の恩恵を受けるというのは筋が通らない。少なくとも健康被害を受けた人々への補償を何らかの形ですべきである。 問題はそうした制度が現在ないことなのである。
似たような制度はあるにはある。公害健康被害補償法である。この法律は汚染原因者からの賦課金を財源として大気汚染被害者へ補償給付を行なうことを定めている。SOxを排出する工場からは総額年間500億円以上の賦課金が拠出されている。だがここでも自動車メーカーの拠出はない。また給付を受けられる患者の新規認定も現在では行なわれていない。いま肝要なのはPMなどによる公害被害者も救済する新たな制度を創設することである。その時に自動車メーカーが応分の負担をすべきことは論を待たないのである。
経済産業省への挑戦状〔完結編〕
2004.08.07
経済産業省への挑戦状〔完結編〕
~温暖化対策のための情報公開請求の結果~
◆はじめに
この『経済産業省への挑戦状』を書き始めてから2年余りが経つ。2年前、私は経済産業省が持つエネルギー情報の開示を要求した。各企業がどれだけのエネルギーを消費したかのデータである。経済産業省はこれを拒否し、私は改めて情報公開法に基づいて資料請求した。 なぜこの請求が必要だったのか、何の意味があるのか、それを記すのが本論を書き始めたきっかけだった。
当時私は衆議院議員2期目で外務大臣政務官の職にあった。時あたかも京都議定書の国会承認の時期だった。温暖化対策は第一義的には環境省の所管だが、京都議定書そのものは国際条約なので外務省の管轄である。 締結するかどうかで政府・自民党内でも激しく議論がなされていた。職務上、私もちょうどその渦中にいた。そこで本稿でもその経緯を日誌として綴ってみた。
一方、肝心の情報公開請求の方は、開示された情報を解析するのに2年がかかってしまった。この「完結編」ではその顛末を記してみたい。2年の間には様々な変化があった。私自身は川口順子外相と台湾問題をめぐり意見の衝突があり、政務官を辞任した。衆議院選挙も一回あった。昨年7月にはこの日記にも環境大臣政務官としてしばしば登場した畏友・奥谷通衆議院議員が逝去された。51歳という若さで病に倒れたことは惜しみても余りある。「歳歳年年人同じからず」の感がある。変わらないのは議定書がいまだに発効していないという現実である。日本のCO2排出に歯止めがかからないことも変わりがない。
◆なぜ情報公開請求をしたか
情報公開請求の結果について述べる前に、まずなぜこの請求に至ったかを簡単に振り返ってみたい(詳しくは『経済産業省への挑戦状〈上〉』を参照願いたい)。
日本全体で排出される二酸化炭素の量は年間12億トンに上り、その最大の排出源は産業界である。しかし各事業者にはどれだけの二酸化炭素を排出したかを公表する義務はない。中には環境報告書などで公表している例はある。だがあくまでも自主的なものにとどまっている。
そこで私は法律を改正して企業に二酸化炭素の排出量公表を義務付けるべきだと主張してきた。02年の京都議定書の批准に合わせてこうした国内制度を導入すべきだと考えていた。公表したからといってすぐに排出が減るとは限らない。それでも透明性を高めることで無際限な排出には自制が働くだろう。またどこがどれくらい出しているのかの数値が分からなければ有効な対策も取りえない。
残念ながら法改正は実現しなかった。経済産業省などが強く反対したためである。しかし現行法の中でも企業のCO2排出を推計できるものが一つあった。省エネ法である。この法律は一定規模以上の工場に、毎年どれだけのエネルギーを使ったかを経済産業省に届けることを求めている。消費した石炭や石油、天然ガスなどの量を報告しろというわけである。この数値が分かればCO2の排出量を計算できる。そこで経済産業省に資料を出すように言った。回答はNoだった。法改正もしない、省エネ法の資料も出さないというままで放置するわけにはいかない。そこで情報公開法に基づいた請求をしたわけである。
◆気候ネットワークによる分析
情報公開請求をしたのは02年の2月だった。それから数か月の間、公開された資料が順次私の事務所に届いた。資料には00年度の一年間にどの工場がどれだけの燃料を使用したかが記されている。参考までに典型例を掲げておく。
〔王子製紙富士工場〕 http://www.catv296.ne.jp/~mizunokenichi/save%20oji.jpg
実を言うと各社がどれだけのA重油を使ったか、石炭を燃やしたかということに興味があるわけではない。 知りたいのはCO2の排出量なのである。係数を掛ければこれは算出できる。例えば石炭ならば一般炭を1キログラム燃やせば約650グラムの炭素(CO2に換算すると2.39キログラム)が排出される。LNGならば1キログラムあたりCO2が2.77キログラムという具合である (注1)。
しかし口で言うほど簡単な作業ではない。事務所に届いた資料の量は段ボール箱で二箱分くらいになる。これらの数値にすべて係数を掛けて計算をするというのは膨大な労力がいる。自分で請求しておきながらこういうのも気が引けるが、実態としては手に余る状態だった。そこで「気候ネットワーク」に資料の解析を依頼した。「気候ネットワーク」は地球温暖化防止に取り組む代表的なNGOであり、私も交流があった。そしてこの「気候ネットワーク」が多大なご苦労の末、各事業所のCO2排出量を算出し、結果を今年の6月2日に記者発表するに至った。大変な作業をされたことに感謝申し上げたい。解析結果の詳細は「気候ネットワーク」のホームページ(http://www.kikonet.org/)に掲載されており、以下述べる内容もかなりそれに依拠している。
◆石油・化学・鉄鋼業界が開示せず
省エネ法は、燃料や電気を大量に使った事業所に、消費量を国に報告することを義務付けている。燃料の場合は原油に換算して年間3000キロリットル以上、電気の場合は1200万kwh以上である。 対象となる工場数は燃料が全国で2505、電気が3403となる。両方の対象となっているのが1904あるので、重複を除くと4004の工場が何らかのエネルギー消費量を報告したことになる(注2)。 このうちデータを開示しなかったのは687工場なので、全体の17%ほどになる。不開示というのは黒塗りで資料を出してきたということである。 例としては次のようになる。
〔新日本製鉄君津製鉄所〕 (燃料についての報告)
http://www.catv296.ne.jp/~mizunokenichi/save%20sinnitetu.jpg
興味深いのは業種によって対応がかなり分かれたことである。不開示率が高かった業種は次の通りである。
業種/不開示率/備考
石油製品・石炭製品製造業/54% /52事業所中不開示28
化学工業/50%/584事業所中不開示291
鉄鋼業/43%/259事業所中不開示111
大手高炉は100%不開示
逆にエネルギー多消費型産業の中でも「電気業」(不開示率5%)や「パルプ・紙・紙加工品製造業」(不開示率7%)などは情報公開度が高かった。
情報公開法では一定の理由があれば不開示にすることもできる。今回不開示とした理由としては「事業活動に関する内部情報であり、開示することにより正当な利益を害するため」というものが挙げられている。その判断は建前上、経済産業省が決めることになっている。だが実際には当該企業にお伺いを立ててから決定している。つまり開示するかどうかはその会社の意向といってよい。開示率が低い業界では、開示しないよう何らかの申し合わせをしたのではないかという疑念が当然出てくる。このあたりを関係者に聞いてみた。日本鉄鋼連盟幹部は言う。
「申し合わせはしていない。だが燃料の使用量はコスト情報であり企業秘密にあたるので、各社とも公表しなかった」。百歩譲って個別燃料の使用量は企業秘密だとしよう。そうだとしても二酸化炭素の排出量ならば公表して問題はないはずである。複数の燃料を使えばCO2の排出量からは、どの燃料をどれだけ使ったかは逆算できないからである。せめてCO2排出量は公表義務とすべきである。
◆CO2排出は一部事業者に集中
二酸化炭素は多種多様な部門から排出されている。 しかしそのかなりの割合は一部の大口排出者によって占められていることもこの調査によって明らかになった。開示されたうち最大の排出源だった中部電力碧南火力発電所は年間1087万トンの二酸化炭素を排出している。愛知県碧南市にあるこの発電所には70万kwの石炭火力発電機が3機あるが、ここだけでケニアやミャンマーなどの一国全体よりもCO2を放出していることになる(注3)。
開示されたうちの上位50の事業所だけで日本全体の排出量の 20%を占めている。つまり大口排出者への対策が喫緊の課題だということが分かる。では上位の事業所とはどういうところか。上位50のうち実に48までは発電所が占めている。
例外は26位に丸善石油化学千葉工場(エチレン・プロピレンなどを生産している)、41位に大王製紙三島工場が入っているだけである。他の大量排出源と目される鉄鋼・化学業界などの多くが情報を開示していない以上、ある程度予想されたことといえる。こうした業界も含めばどのような結果になっただろうか。断定的なことは言えないが、かなり上位に食い込んできたことは確かだろう。例えば鉄鋼最大手の新日鉄は今回の開示請求には応じなかったが、社全体でのCO2排出量を5800万トン(02年度)と認めている。これは大手10電力に当てはめれば2位の中部電力と3位の関西電力の間に位置する値である。こうした企業の情報が開示されていれば、大口排出者への集中度はさらに高まっていたはずである(注4)。
断わっておくが、大量に排出しているから悪いと即断するつもりはない。エネルギー多消費型産業が上位にくるのは当然であって、それ自体が悪いわけではない。問題は努力しているかどうか、つまりCO2排出量が増えているのか減っているのかの方向性である。だが情報が開示されないとこうした推移さえ分からないのである。
◆石炭火力発電所の問題
CO2の排出が一部事業者に偏っているのはすでに見た。上位5つを掲げてみる。いずれも発電所だったので参考までに発電電力量も表示した。
企業名/事業所名/CO2排出量/発電電力量
①中部電力(株)/碧南火力発電所/10871/ 14527
②相馬共同火力発電/ 新地発電所/10647/13228
③電源開発(株)/松浦火力発電所/10396/12850
④東北電力(株)/原町火力発電所/10327/13232
⑤中部電力(株)/川越火力発電所/10061/25259
(単位:CO2は千t、発電電力量は100万kwh)
興味深いのは、上位4位までがすべて石炭火力発電所だということである。5位にやっとLNGを燃料とする中部電力川越火力発電所が入ってくる。1位と5位を比較してみると面白い。同年の発電量を見ると1位の碧南火力(石炭火力)が145億kwhなのに対し、5位の川越火力(LNG火力)が253億kwhである。石炭火力発電というものが発電量の割に、いかに大量にCO2を排出しているかが分かる。
先に大量に排出しているから悪いとはいえないと書いたが、石炭火力発電の場合は少し違う。発電というのは石炭を使わなくても可能である。よりクリーンなLNGなどに代替しうる。製鉄の高炉では還元剤としての石炭が不可欠なのと事情が異なる。しかもこうした石炭火力発電所は最近も新設されているのだ。石炭というと時代遅れの遺物のように思う方もいるかもしれない。だが実際には上位4つの石炭火力発電所の運転開始はいずれも1990年代である。すでに地球温暖化は大きな問題になっていた。
それにもかかわらず逆行した動きが進んでいたわけである。そして安い石炭をあてにした石炭火力発電所はいまなお建設が進められているのである(例えば電源開発の磯子火力発電所新2号機は08年度建設着工、09年度運転開始の予定である)。
◆第二ステップに向けて
この情報公開請求をした02年は温暖化対策にとって重要な年だった。京都議定書が批准され、政府の温暖化対策の基本方針である地球温暖化対策推進大綱が改定された。そして今、再び大切な節目を迎えようとしている。来年度から温暖化対策のための第二ステップに入るからである。それを受けて大綱も今年度中に再改定されることになっている。 02年の大綱改定時に「ステップ・バイ・ステップのアプローチ」という考え方がとられた。02~04年を第一ステップ、05~07年を第二ステップ、08~12年を第三ステップとして順次必要な対策をとるというわけである。排出削減の進み具合を見極めながら段階的に取り組みを強化していくことになる。京都議定書で日本は温室効果ガスの排出を基準年の1990年から6%削減することを約束している。ところが02年度時点で逆に基準年より7.6%も増えてしまっている。このままでは約束が達成できそうもない。来年度からの第二ステップでは対策強化が必要である。そしてその具体策を決めるのが今年度中なのである。
では大綱の改定にあたっては何を盛り込むべきだろうか。以上述べてきたこととの関係でいえば、まず大企業の排出量の公表は当然である。そもそもこれは第一ステップから導入されるべきことだった。 遅ればせながら義務化すべきである。会社四季報を見れば売上高や経常利益、従業員数など各種の基本的な企業情報が載っている。それと同じように、CO2の排出量は常識として提供されるべき情報なのである。
EUでは今年2月からEPERという汚染物質排出登録制度が始まり、CO2を年間10万トン以上排出する施設は報告が義務付けられるようになった。 この情報は欧州環境庁によりウェブ上で公開されている。日本でもPRTR法に基づいて各事業所は化学物質の排出量を届け出ることになっている。届出の対象となっている化学物質は354種類あり、オゾン層を破壊するフロンもこれに含まれている。そして排出量の情報は開示請求をすれば誰でも手に入れることができる。CO2の排出量だけは非公開というのは不合理である。
現在の省エネ法では経済産業省が各工場の燃料使用情報を抱え込んだまま表に出していない。そもそも情報を独占して一体何の役に立っているのだろうか。その方がよっぽど疑問である。なお情報の保存期間は経済産業局ごとに異なる。最短は関東・中部・近畿・四国・九州の各経済産業局の1年間である。 これではせっかくの情報が死蔵されたまま、すぐに廃棄されているのではないかとの感をますます強くせざるをえない。 国内でも先進的な自治体は温室効果ガスの排出量報告・公表に独自に取り組んでいる。東京都や三重県などである。三重県は01年に施行された「生活環境の保全に関する条例」で事業者に温暖化への対策計画を提出させている。この中には温室効果ガスの排出量情報も含まれている。そしてこの計画は県庁のホームページで公開されている。環境省の調べによると今年5月時点で条例に基づいて温暖化対策計画の策定や排出量の公表などを義務付ける制度が存在しているのは9都県3政令指定都市に上っている。
ただ自治体によっては計画の提出は求めても公表は義務付けていなかったりするなど、内容はまちまちである。第二ステップでは全国共通ルールで国が先駆的な制度を導入することが求められる。具体的には二つの方法が考えられる。一つは地球温暖化対策推進法を改正して、企業に対し毎年の温室効果ガスの排出量情報の報告・公表を義務付けることである。もう一つのやり方はPRTR法を改正して、化学物質に加え温室効果ガスも対象にするというものである。いずれにしても報告・公表を義務化することが大切である。これは決して唐突な考えではない。 国の内外に似たような例が数多いのは以上見てきた通りである。
◆単なる情報公開を超えて
だが事ここまで来て、排出量の公開だけすれば、それで良しというわけにはいかない。いま京都議定書を守れるかどうかの瀬戸際に立っているのである。 日本はすでに一度、地球温暖化防止のための国際約束を果さなかった「前科」がある。1992年の気候変動枠組条約は2000年までに90年レベルの排出量に戻すことを目標としていた。結果はそれとほど遠いものに終わった。2000年度の日本のCO2排出量は90年比10.4%増だった。今度こそ国際約束を守らなければならない。まして日本で結び、日本の古都の名が冠された条約である。しっかりとした対策が求められている。 よく環境問題への対策として三つの手法があるといわれる。①規制的手法②経済的手法③自主的取り組みである。第二ステップでこれらの手法をどう織り交ぜるかについて簡単に触れて本稿のまとめとしたい。
まず①の規制的手法である。温暖化対策としては直接規制は必ずしも有効でないとされる。 ダイオキシンやSOxのように人体に悪影響を与えるものならば厳格に排出規制しなければならないが、CO2はそうした有毒物質ではない。また排出源があまりにも多く、規制がかけづらい面もある。それでも規制的手法がまったく不要ということではない。 例えば石炭火力発電所の新設には何らかの歯止めがあってもよいだろう。発電所の建設に制限をかけた例は過去にもある。1980年に“代エネ指針”によって石油を原料とする火力発電所の新設を原則として禁止している。これは二度のオイルショック経験から石油依存度を下げるためにとった政策だった。 今度は環境面から石炭火力を規制するということを考えるべきではないだろうか(注5)。
一番脚光を集めているのが②の経済的手法である。経済的なインセンティブを与えて望ましい方向に誘導していくというものである。炭素税(環境省は温暖化対策税と呼んでいる)や国内排出量取引がこれにあたる。私も温暖化対策に最も有効な手段はこれだと思う。 特に炭素税は産業・運輸・民生のいずれの部門でも排出抑制効果が期待できる唯一の手段と考えられる。 また排出量取引も確実に一定量を削減できる効果的な手法である。第二ステップでは少なくとも部分的な導入は実現すべきである。ただこうした新制度を導入するためにも、排出量の公表義務化は必要となる。炭素税の場合、どの段階で課税するかにもよるが、CO2の排出量に応じた課税ならば排出量情報は必須のものとなる。排出量取引の場合は特にそうである。どこが何トン出しているかが分からなければ取引も何もなしえないからである。公表義務化はこうした施策のいわば大前提といえる。
最後に③の自主的取り組みについて触れておきたい。経団連は十年一日の如く自主的取り組みを強調する。自主的に取り組むことは大いに結構である。 問題はそれで十分なのかどうかということである。 経団連や経済産業省は十分効果をあげているという立場で、私は不十分だと考えている。確かに産業界からの排出量は伸びてはいない。02年度は90年比でマイナス1.7%とむしろ下がっている。景気低迷のため生産活動そのものが減った面もあろうし、自主的な省エネ努力もあっただろう。努力をまったく評価しないわけではない。だが現大綱では産業部門の削減目標は7%とされている。まだまだ目標に達していない。
また今回の情報開示請求に応じなかった企業も多い。自主的取り組みには評価すべき点もあるにせよ、それに加えて最低限のこと“つまり排出量の公表”は法律で義務化するというのが正しい政策判断だと思う。 ところがその最低限のことにも反対する声がいまだに存在している。経済産業省で環境問題を担当している幹部はこう言う。「企業がCO2排出量を公表すること自体は良いことだが、あくまでも自主性に任すべきであり法律で義務付けるべきではない」。 こうした反対論を乗り越えて必要な施策を成し遂げなければならない。 実を言えば、排出量情報の公表というのは二酸化炭素の削減策ではない。炭素税や排出量取引といった削減の具体策の前提にすぎない。いわば入り口である。入り口での押し問答になってしまっていることには忸怩たる思いもある。これに時間を掛けているわけにもいかないからである。すみやかに入り口を通過して本格的な具体策作りに入らなければならない。地球を温暖化から守るために残された時間はもうそれほどないのだから。
(注1) これだけだと一見、石炭の方がCO2の排出が少ないようにみえるが、そうではない。一般炭1kgはLNG1kgの半分弱の熱量しかない。 そのためエネルギー当たりのCO2排出量は一般炭の方が1.8倍ほど多くなる。
(注2) 省エネ法でエネルギー使用量を報告するのは工場単位であって、企業単位ではない。電力会社を例にとれば会社全体としてのデータではなく、発電所ごとの報告となる。また燃料3000kl以上、電気1200万kwh以上というのは、情報公開請求の対象となった00年度時点のことである。その後03年4月より改正省エネ法が施行され、報告が義務付けられるのは燃料で1500kl以上、電気で600万kwh以上にまで引き下げられた。また報告対象となる業種も従来は5業種(製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業)に限られていたが、この改正時にすべての業種へと広がった。それまでは報告義務がなかったオフィスビル・デパート・ホテルなども一定以上のエネルギーを使用すれば定期報告をすることになったわけである。これにより現在では報告義務のある事業者数は電気・熱の重複を除いても10578に増加した。
(注3) 碧南火力発電所ではその後01年11月と02年11月にそれぞれ100万kwの石炭火力発電機が運転開始したので、現在は5機となっている。
OECD資料によれば01年のエネルギー起源CO2排出量はケニアが810万トン、ミャンマーが710万トンである。
(注4) 大手電力会社の社全体としてのCO2排出量は各社の環境報告書(03年度版)を参照した。上位の順位は次の通りである。
①東京電力 10740万トン
②中部電力 6268万トン
③関西電力 3684万トン
④中国電力 3460万トン
⑤東北電力 3156万トン
(注5) “代エネ指針”は正しくは「工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入の指針」といい、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に基づいて経済産業大臣が定める。1980年の指針では石油火力発電所の新設は原則禁止とされていたが、98年の改定で一部容認に転じた。
印旛沼浄化計画がついに始動
2004.07.01
「印旛沼浄化計画がついに始動」
印旛沼の水質は全国の湖沼の中で悪い方から二番目です。しかもこの水は飲料水にも使われています。
全国ワースト1位の佐鳴湖の水は飲料用にはなっていませんから、飲用の水源としては印旛沼は全国最悪の水質なのです。もちろん各家庭の水道管に送られる前には浄水場(千葉市花見川区柏井にある)で浄化するので、直接健康を害することはありませんが、元の水が奇麗なことに越したことはありません。
その印旛沼浄化のための計画がようやく動き始めました。今年度から国の予算に印旛沼の河川環境整備事業費が付くようになったのです。事業をするのは県ですが、国が半額補助をします。これまでの対策は下水道の整備や“水をきれいに”という啓発活動・ポスター作りなどに限られていましたので、沼そのものを浄化しようという本格的な試みは今回が初めてとなります。
事業は平成22年度まで7年の年月と約150億円をかける見込みです。今後の調査によって何をやるかの詳細が決まる予定ですが、沼底に溜まっているヘドロの除去 水生植物を繁殖させることによる自然浄化が大きな柱となりそうです。具体策の決定にあたっては国や県が一方的に決めるのではなく、住民やNPOの意見も聞きながら進めることが大切です。私も議員として行政をチェックしながら建設的な提言をして、全国に誇れる環境保全事業にしていきたいと思っています。
*湖沼の汚濁は一般的にCOD(化学的酸素要求量)という値で表わす。印旛沼に対しては行政側が目標値として3mg以下という環境基準を昭和45年に定めたが、一度も達成されたことはない。
◆全国湖沼水質ワースト5(02年度・COD年平均値)
佐鳴湖(静岡県) 11
印旛沼(千葉県) 9.1
長 沼(宮城県) 9.0
児島湖(岡山県) 8.9
春採湖(北海道) 8.7
単位はmg/リットル
〔追補〕
印旛沼についてはこれまでこの「けんいちの主張」欄に00年5月、01年11月、03年10月の3回にわたって小論を書いています。そこでは自然再生法に基づく協議会の設立を提唱しました。これはいまだに実現はしていません。ただその代わりに国・県・市町村・学識者・NPO・土地改良区など関係者が集まった「印旛沼流域水循環健全化会議」で水質浄化と治水についての討議がかなり進展してきました。そこで現時点ではこの枠組を充実させることが現実的と考えています。
今回、「印旛沼河川環境整備事業費」という国の予算がついたことにより、今後水質浄化の最大の柱はこの計画になっていきます。計画の詳細は、水循環健全化会議の中に置かれた“水質改善技術検討会”で策定されることになりますが、こうした具体的計画を作るにあたっても住民・NPOなどの声を十分に聞くことが求められています。
私たち若手議員が考えた 「北朝鮮制裁法案」の意義
2004.04.01
「私たち若手議員が考えた 「北朝鮮制裁法案」の意義」
特定船舶入港禁止法の中身について分かりやすく解説。月刊誌「正論」04年5月号に掲載
◆はじめに
北朝鮮とどう向きあうかは日本外交の最も大きな課題である。同時に重大な安全保障上の問題でもある。なにしろ相手は「軍事優先政治」を堂々と公言している国である。現に飢餓に苦しむ国民を横目に核やミサイルの開発に突き進んできた。また罪もない日本国民をいきなり拉致するという犯罪行為も繰り返してきた。
日本政府は「対話と圧力」という方針を掲げている。基本的にはこれは正しい。対話は重要である。しかし話せば分かるという相手でもない。圧力をかける用意も必要である。ただ問題はこれまでは圧力をかけようにもかけることさえできなかったことなのである。圧力としてまず思い浮かぶのが経済制裁である。だがその実施には国連決議などを待たなければならなかった。裏を返せば日本単独の判断では発動しえなかった。今までの法律が不十分だったためである。
そこで今年の通常国会で法改正が行なわれた。第一弾が外為法の改正である。これによって必要があれば日本単独の判断でも経済制裁が可能になった。第二弾として北朝鮮船の入港禁止法案も議論の俎上にあがっている。これらの法案は議員立法として進められてきた。私も当初から策定に関わってきた。本稿ではまずこれまでの経緯を概観してみたい。続いて現在成立に向けて鋭意努力中の入港禁止法案について内容を詳しく見てみたい。
◆対北朝鮮外交カードを考える会
北朝鮮に対しては甘い姿勢を取ることで軟化を促すという考え方があった。韓国の「太陽政策」はその典型である。 日本もかつてその考えに立っていた。90年代のコメ支援がそれである。コメ支援は95年から2000年にかけて5回にわたって行なわれた。北朝鮮に供与した政府米は合計117万トンである。とりわけ2000年10月の支援は要請量をはるかに超える50万トンという大規模なものだった。
自国民を飢えさせて他国に支援を頼み、一方で核を開発するなどという馬鹿な話はない。その上、支援している国をミサイルの射程に捉えるなどということがあって良いはずがない。ところが現実にそういうことが起きているのである。それにもかかわらずあえて支援したのは善意で接することで融和を図ることができると考えたからである。だがそれは幻想だった。せっかくの支援は北を増長させることは
あっても拉致問題などの解決にはつながらなかった。 この点はあらためて反省してみるべきだろう。
「対話と圧力」という言葉を政府が使うようになったのはここ1年ほどである。俗にいえばアメとムチを両方準備するということである。これは決して間違っていない。 対話の窓口は開けつつも圧力もかけられるようにしておく。対話を進めるためにもこれは必要である。圧力をかけなければ対話にさえ応じない相手だからである。 こうして圧力という掛け声が上がるようになった。だが実際に日本政府が取りうる手段は限られていた。例えば98年にテポドンを三陸沖に打ち込まれた時に抗議として行なったことは、①チャーター便の運航停止、②KEDOへの協力の見直し、③食糧支援の凍結 というくらいである。このうち①と③は支援を止めただけのことである。つまりアメを与えなくなっただけでムチではない。
この程度の対応しか取らなかったのは当時の政府に毅然とした姿勢が欠けていたというだけではなく、法律上それ以上のことができなかったためでもある。本格的な経済制裁は不可能だったのである。 法律に不備があれば直せばよい。まして北朝鮮が拉致事件などで不誠実な態度を取り続ける以上なおさらである。だが政府からはその熱意が感じられなかった。それならば議員立法という方法がある。そう思った自民党の衆参若手議員が02年12月に集まって「対北朝鮮外交カードを考える会」を結成した。メンバーは山本一太、菅義偉、河野太郎、増原義剛、小林温の各氏と私の6名である。会の名称は山本氏がつけた。法整備をすることが北朝鮮という厄介な相手との交渉カードになるという思いが込められている。
◆二つの制裁法案
この会が準備した法案は二つある。外為法の改正案と船舶入港禁止法案である。外為法というと円高ドル安などの法律と思う向きもあるかもしれない。もちろんそれも含まれる。だが「外国為替及び外国貿易法」という正式名称が示す通り、対外取引全般を管轄している。送金や貿易の制限といった経済制裁もこの法律に規定されている。ただ従来は発動要件が厳しかった。国連決議もしくは多国間の合意があってはじめて発動できる形になっていた。国際社会が協力してどこかの国に制裁を加える時は日本もそれに参加できるということである。逆に言うと日本単独の判断での発動はできなかった。先のテポドン発射の時には国連決議はない。そうなると制裁は行なえない。そこで我々の改正案では発動要件を緩和した。国際社会全体として実施する時に参加できるのは当然のこととして、それに加えて日本の平和と安全のために必要があれば単独での制裁も可能とした。
もう一つの船舶入港禁止法は例えば万景峰号を入港させないということである。拉致や工作に関係したこの船が自由に行き来していることは国民感情としても納得しがたい。現行法では止めることができないので新法を準備した。外為法がモノとカネの流れを規制できるのに対し、こちらはヒトの往来も止められる。モノとカネについても、いくら外為法で制裁を発動しても船舶が往来している限り不正輸出や不正送金の可能性がつきまとう。すべての荷物を厳重に検査することは不可能だからである。なにしろ現在外国貿易のために開かれている港は国内に120もある。 制裁を実効性あるものにするためには運搬手段を元から絶たなければ駄目である。外為法による経済制裁を担保するためにも入港禁止法が求められている。
なおどちらの法案も成立したらすぐに発動されるというわけではない。必要があれば政府が経済制裁や入港禁止を行なうことができるというのが法律の趣旨である。北朝鮮がまともな国になれば発動しないという余地は十分に残されている。
議論が先行したのは外為法の改正である。入港禁止法が新法だったのに対し、外為法が改正だったという面もある。「外交カードを考える会」では03年2月に外為法の具体的な改正案と入港禁止法の骨子を発表した。拉致問題に携わる議員らとも相談の上、まずは熟度の高い外為法改正に全力を注ぐこととした。残念ながら党内手続きをしているうちに昨年の通常国会は会期末になってしまい提出には至らなかった。しかしその動きが無駄になったわけではない。
秋の衆議院総選挙で「拉致被害者家族会」「救う会」がアンケートを行なった。その結果当選者の実に81%が外為法改正に、76%が入港禁止法制定に賛成した。このことが法案成立に大きく弾みをつけることになった。今年1月に開会した国会では冒頭に外為法改正が取り上げられた。自民・公明・民主の各党ともに総論では賛成だったので、三党間で細部の詰めの作業を行なった。こうして自民党原案を一部修正の上、三党共同の議員立法として提出することになる。私も提出者として国会答弁に立った。 共産党だけが反対したが、2月9日に成立した。
◆入港禁止の対象船舶(当初の案)
改正外為法が成立した以上、今度は入港禁止法案に力を傾けなければならない。ここからは「外交カードを考える会」が練り上げた入港禁止法案の内容について見てみよう。
どの船を禁止の対象にするかは法律の根幹である。当初は「怪しい外国船」は入れないということを考えていた。昨年2月に法案骨子を発表した時は拉致・監禁・スパイ行為などに関係した船舶は入港させないという形になっていた。船の怪しさに着目したわけである。最大の不審船である万景峰号が念頭にあったのはいうまでもない。
だが議論の中でこの考えは根本から見直すことにした。 怪しい外国船を止めるという場合、怪しさを証明する必要がある。拉致やスパイ行為に関与したことを立証しなければならない。確かに万景峰号がこうした目的で使われた証拠・証言は集められるだろう。しかし日本に出入りする北朝鮮船は万景峰号だけではない。本当に不正行為を行なっているのは一見普通の貨物船だとも言われている。しかも万景峰号の出入りする新潟港はかなり厳重な警戒が敷かれているのに対し、貨物船は警戒の甘い他の港に出入りしているため不正の実態は捕捉しづらい。こうした貨物船が拉致・監禁などに関わっていたことを証明するのは至難である。そうすると入港は野放しになってしまう。
海上保安庁の調べによると一年間に国内の港に入港する北朝鮮船は01年が1225回、02年が1344回、03年が991回である。この数字はのべ数である。一隻の船が往復して10回入港すれば10回と数えている。うち万景峰号のこの3年間の入港回数は21回、21回、10回である。実は万景峰号は氷山の一角にすぎない。一般の貨物船まで対象にできないとザル法になりかねない。
さらに言えば、怪しい外国船を止めるという形では万景峰号でさえ止められるかという疑問まで出てくる。この船が過去に不正行為に関与していたことは明らかである。しかし例えば5年前に船内で謀議がこらされたことがいくら証明できても、それが現時点で入港禁止にする根拠になりうるだろうか。現在工作員を乗せていることが立証できるならともかく、過去に犯罪に利用されたことを入港禁止事由にするのは難しい。船が悪事を働くのではない。乗っている人間や背後にある国家組織が悪事を働くのだ。船が怪しいから止めるというやり方にはどうも無理があるようである。
◆入港禁止の対象船舶(現在の案)
そこで法案を大きく改めた。万景峰号のみならず北朝鮮船を一律に規制できるようにした。船の怪しさから国の怪しさに着眼点を変えたともいえる。入港禁止とする船舶はまず第一に特定の国籍をもつ外国船である。この場合は北朝鮮船ということになる。だが北朝鮮船だけを対象にしても大きな抜け道ができてしまう。便宜置籍船である。便宜置籍船とは税金対策などのために船の国籍だけを他国に置くことをいう。税金の安いパナマ、リベリアなどに移すことが多い。北朝鮮船だけに限ると税金逃れならぬ入港禁止逃れのために便宜置籍されるとどうにもならない。他国船をチャーターすることも抜け道となる。いまのところ北朝鮮籍以外の船が日朝間を往来することはほとんどないとされる。それは北朝鮮船でも自由に往来できるからである。やはり入港禁止逃れの道は塞いでおかなければならない。
そのため北朝鮮に寄った船も入港禁止の対象とした。パナマ船だろうと中国船だろうと米国船だろうと日本船だろうと北朝鮮に寄港すれば入港禁止となる。ただし過去に寄港したことがある船をすべて締め出すわけにもいかない。遡及はさせない。日本政府が入港禁止を決定したにもかかわらず、それでもあえて北に寄った船を対象にした。北朝鮮に寄港する限り日本船といえども例外ではない。そこで法案の名称も「特定船舶入港禁止法案」に変更した。それまで「特定外国船舶入港禁止法案」と呼んでいたが、「外国」を抜いたわけである。
すぐに出てくる疑問は北朝鮮に寄港したかどうか分かるのかということである。船が入港する時には入港届など様々な書類を提出する。現在の入港届は直前に出港した港を記入するだけで、それ以前にどこに寄っていたのかまでは分からない。ここを改正して最近数か月間のすべての寄港地を報告させるべきだという考えもあるだろう。だがその考えは採らなかった。日本に入港する外国船は年間11万隻ほどある。 日本船も含めれば数はさらに増える。その99%は北朝鮮と何の関係もない。そうした船舶に新たな義務を課すのは大きな反発を招きかねない。そうなると法案そのものの成立さえ危うくなってしまう。
わざわざ報告させなくても十分効果はある。北に寄った船の入港を違法だとしておくこと自体に意味がある。違法行為である以上、疑わしい船舶に対しては海上保安庁法に基づいて海上保安官が立ち入り検査できる。検査の結果、違法性が明らかになれば罰則もかかってくる。ちょうど車の無免許運転の取り締まりと似ている。運転している人が全員免許証を持っているかどうかは外見では分からない。 それでも無免許運転を違法行為としておくことで、必要があれば警察官が免許証の提示を求めることができるのと同じである。
◆航空機はどうなのか
航空機は対象にしないのかと思われる方もいるだろう。 我々の案では飛行機について触れていない。なにも空路は手つかずのままでよいと考えているわけではない。航空機は現行法でも止められるのであえて新法に盛り込むまでもないということである。日朝間に定期便はない。定期便を飛ばすためには普通二国間の航空協定を結ぶ。飛ばしたくなければこれを結ばなければよい。チャーター便はかつて年間80便以上も飛んでいたことがある。02年を最後に途絶えているが、今後申請がないとはいえない。しかしこれも航空法に基づく許可が必要である。空路を止めたければ許可を与えなければよい。テポドンが発射された98年にはチャーター便を認めない方針を打ち出し、翌年まで不許可が続いた。83年にソ連が大韓航空機を撃墜した時には日ソ間の定期便・チャーター便を一時停止したこともある。航空機は現行法でも止めることができ、現に実施したこともある。そこで新法に盛り込むのは蛇足と考えた。
なお現在、東京都などで北朝鮮船の入港禁止を狙って港湾条例を改正しようという動きがある。都民の生命・身体・財産を害する恐れのある船には港湾を利用させないという条項を設けるわけである。意図することは理解できる。 だがこれは船の怪しさに着目している。この場合、入ろうとする船が都民の生命・身体・財産を脅かしていることを証明するのがかなり難しい気がする。
◆発動要件
ではどのような場合に入港禁止措置を発動するのか。法案にあるのは「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき」という表現である。これは外為法の日本単独での経済制裁の発動要件と同じにしてある。
北朝鮮が核実験やミサイル発射など平和を直接脅かす行動をとれば当然入港禁止を実施できる。薬物密輸の横行で国民生活の安全が脅かされていると判断した時も同じである。 拉致はどうか。「我が国」という場合、国民も含まれる。日本国民を拉致しておきながら、その解決に誠意ある態度が見られない時も発動要件は満たす。要するに圧力をかけなければ物事が進展しないと政府が判断したならば発動できるのである。
他方、乱用も戒めなければならない。入港禁止を行なう時は必ず閣議決定を経ることとした。これも改正外為法と同じである。入港禁止というのはかなり大胆な措置である。
平和と安全という高度な判断が求められる。単独の大臣の決定で実施すべきことではない。港のことだからといって国土交通大臣だけの判断で発動するというのはかえって不自然である。内閣全体として取り組むべき課題である。
また事後の国会承認も必要とした。 閣議で定めるのは発動対象の国、並びに入港禁止の期間などである。例えば「北朝鮮船及び北朝鮮に寄港した船舶は今後6か月間は入港させない」ということを決めることになる。期間は極めて重要である。というのもこの法律は発動すれば北朝鮮船は一律に入港禁止となる。この船は良くてこの船は悪いという選別はしていない。選別する合理的な根拠がないためである。すべて入港を認めるか、すべて認めないかで中間はない。段階的な発動というのは入港禁止の期間で調節するしかない。仮に年間1000隻が来るとして、入港禁止期間を3か月とすれば250隻が止まることになる。半年ならば500隻で、1000隻すべて締め出したければ1年間を通じて発動すればよい。もちろんこれは船舶が平均的に往来すればという仮定に基づく話だが、期間の長さによって圧力の強弱を調節するわけである。
期間内に相手が誠意を見せるということもありえる。 この場合は入港禁止措置を解除できる。逆に期間が終わってもまだ必要性が残っていることもあろう。その時は延長も可能にしてある。なお法案では遭難などの場合の入港は容認している。また閣議で特に定めればその他の例外もありえる。大地震が起こった時の支援船やKEDOで働く日本人技術者の帰国のための船などがこれにあたる。
◆国際法との関係
ところで他の国はこのような法律を持っているのだろうか。実はそれほどでもない。少なくとも特定の国の船舶を入港禁止にするという法律は多くはない。一番近いのはアメリカのトリチェリ法だろう。これはキューバ制裁の一環として1992年に成立した法律でキューバに180日以内に寄港した船は米国に入港させないというものである。 例が多くないからといって入港禁止法が国際法上問題があるというわけではない。むしろ北朝鮮のような無法国家が近くにない国はわざわざ制定する必要がないということだろう。ここで一般国際法との関係を見てみたい。まず領海については無害通航権が国際法で確立している。北朝鮮船だからといって日本領海を通るだけならそれを阻止することは難しい。だが港や内水(瀬戸内海など)の場合は違う。入れるかどうかは主権国家の裁量に任されている。 入港禁止法を作るかどうかはその国の判断といえる。
では日本が締結した条約との関係はどうだろうか。最も関係が深いのは1923年に成立した「海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程」である。日本も1926年に加盟している。この条約は締約国に他の締約国の船舶に対し均等な待遇を与えることを義務づけている。そこだけ見ると特定の国の船舶を狙い撃ちして入港させないのは問題となりそうである。だがこの規程も第16条で安全保障上の理由での例外を認めている。それを持ち出すまでもなく北朝鮮はこの条約に加盟していない。仮に今後加盟したとしても日本は北朝鮮を国家承認していないので、本条約は日朝間には適用されない。要するに北朝鮮に発動する限り問題は生じない。
二国間条約との関係はどうだろうか。日本は約40か国と通商航海条約や海運協定を結んでいる。アメリカ、イギリス、中国、韓国、ロシア、オーストラリアなど日本の主要貿易相手国はほぼ網羅している。ここでは相手国の船舶に対し差別的な取り扱いをすることを禁じている。こうした国々に対して発動するのは条約を破棄しない限り無理だろう。しかし北朝鮮とそのような条約があるはずもない。 確かに入港禁止法が発動されれば条約を結んでいる国々の船舶も入港禁止にはなりうる。例えば北朝鮮に寄港した中国船は日本に入れなくなる。だがこれは決して差別的な取り扱いにはあたらない。中国船だろうと米国船だろうと日本船だろうと同じことをすれば入港禁止となるからである。
つまり北朝鮮を対象にする限り国際法にも条約にもなんら抵触するものはない。ただ海洋国家日本としては船舶の自由往来は重要な原則である。日本が妙な法律を作ったと第三国に思われるのも得策ではない。そこで法案の第8条に「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない」と入れておいた。あらぬ誤解を招かないための入念規定といえる。
◆入港禁止法の成立に向けて
この案が正式に自民党内で議論され始めたのは今年の1月29日である。安倍晋三幹事長も極めて前向きである。 自民・公明両党の間では通常国会で成立させるという大筋の合意もある。成立すれば当然北朝鮮は反発するだろう。「強硬には超強硬で対抗する」などというお決まりの声明が出てくるかもしれない。だが自らが勝手なことをするだけしながら圧力はかけるなという理屈は通らない。
国内にも反対や慎重の声はある。圧力でなく対話で解決すべきだという論調である。私も対話は重要だと考えている。とはいえ善意だけで通じる相手でないことは歴史が証明している。圧力の用意も必要である。また船が止まると海産物など日朝貿易で生計を立てている人たちに影響があるという指摘もある。影響を受ける人がいるからといって法律そのものが不要だということにはならない。発動の際には予算面などで一定の配慮を考えた方がよいというだけのことである。
そうした中「わざわざ新法を作らなくても現行法で対応できないのか」という声もある。最後にこれについて触れてみたい。現在の法律では北朝鮮船だからといって入港を阻止することはできない。 ただ今年の通常国会で油濁損害賠償保障法という法律が改正される。これによって無保険船の入港を禁止することができるようになる。背景にあるのは座礁船舶の問題である。座礁した船を撤去する責任は船主にある。だが船が保険に入っていないため船主にその資力がなく結局は放置されるということが頻発した。一昨年に茨城県沖で座礁したまま捨て置かれた北朝鮮船チルソン号はその一つである。そこで法改正して保険への加入が義務づけられ、今後は無保険船は入港禁止となる。北朝鮮船の保険加入率は際立って低い。日本に入港する外国船の保険加入率が平均73%なのに対し、北朝鮮船はわずか3%にすぎない。こうなると多くの北朝鮮船は実態としては締め出される。だから新法は不要ではないかという声も一部にはある。その考えには疑義がある。これはあくまでも保険の有無で入港規制をしているにすぎない。どこの国の船だろうと保険に入れば入港を認めざるをえなくなる。 やはり別途、「特定船舶入港禁止法」は必要なのである。
私たちが用意している入港禁止法が成立すれば日本外交の選択肢が広がる。北朝鮮というのは一筋縄ではいかない相手である。外交カードは多いほどよい。しかも圧力をかけうるということは抑止にもつながる。彼らがこれ以上の無法行為を自制することも期待できる。幸いこの法案には国民の強い支持もある。読売新聞の世論調査では80%の人が賛成している。これに応えるのが立法府の責務でもある。 私自身も立法府の一員として成立のために全力を尽くしていきたい。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月