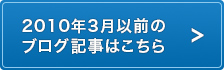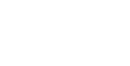- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
宇宙開発について
2002.10.15
「宇宙開発について」
日本版NASAの誕生。その意義と役割とは。
NASAという名前を聞いたことのない人はいないだろう。アメリカ航空宇宙局のことである。アポロ計画やスペースシャトルはあまりにも有名である。NASAはアメリカの非軍事部門の宇宙開発を一手に引き受けている。これに対し日本では宇宙開発を推進する機関が二本建てになっていた。宇宙開発事業団(NASDA)と宇宙科学研究所(ISAS)の二つである。H‐ⅡやH‐ⅡAなど大型のロケットを開発してきたのは宇宙開発事業団であり、1970年に日本初の人工衛星の打ち上げに成功したのは宇宙科学研究所だった。役割分担としては宇宙開発事業団が実用衛星の打ち上げを推進したのに対し、宇宙科学研究所は学術・研究に力点を置いてきた。ロケットの種類でいえば前者の主力が液体燃料ロケットであり、後者は固体燃料ロケットである。
所管官庁は前者が旧科学技術庁ならば,後者は旧文部省だった。 この両機関が今度統合される運びになった。より正しく言えばこれまで航空部門を中心に研究をしてきた航空宇宙技術研究所(NAL)も含めて三機関が統合され、新法人が設立される。行政改革の流れの中、関連する機関は統合し効率的な研究や開発を進めることになったからである。今後の日本の宇宙開発は新設される法人が一元的に管轄することになる。いわば日本版NASAの誕生ともいえる。新機関は宇宙航空研究開発機構(仮称)と呼ばれ、来年10月に正式に発足する予定である。 まもなく開会する臨時国会でその設置のための法案が可決される見込みである。これをきっかけとして日本の宇宙開発がますます進んでいくことを期待したい。
ところで宇宙開発というのは莫大な費用がかかる。それに見合うだけの意味があるのかという批判は常にある。端的にいえば「月に行ったからといってそれが何の役に立つのだ」という批判である。月着陸のアポロ計画もそうした批判を受け、縮小を余儀なくされた。当初の計画では10回の月面着陸を予定していたが、実際に月着陸船が打ち上げられたのは7回に終わった(うち一回は事故のため月面着陸しなかったので月に降りたのは6回)。そしてその後30年間、人類は月に行っていない。
もちろん宇宙開発に実用性がないわけではない。気象衛星・資源探査衛星・通信衛星などはすでに生活に役立っている。来年春には日本初の情報収集衛星の打ち上げも予定されているが、これは日本の安全保障や災害対策などに役立つはずである。さらにスペースシャトルなどで宇宙空間に出ることで無重力状態を利用して地球上でできないようなさまざまな実験を行うことも可能になる。また宇宙ロケットという最先端技術に投資することは関連産業の育成にもつながる。
それでも予算がかかりすぎるという批判がつきまとうのも事実である。費用対効果で見れば、宇宙よりももっと他の分野に投資した方が有効だという意見にも一理はある。そうした声を受け、宇宙開発事業団の予算額は3年連続減少し1476億円にとどまっている。だが宇宙開発とは単に目先の利益だけを追い求めて行なうべきものではない。真理の探求であり、人類の可能性の挑戦なのである。科学技術が実利だけを追求するので本当によいのだろうか。夢も必要である。古来、宇宙は人々の夢をかきたててきた。それを考えれば宇宙関連予算を削減する最近の風潮はおかしなものである。
まして宇宙開発には他の意味もある。宇宙への進出によって地球というものを見つめ直すことができる。つまり人類の意識革命につながりうる。日本を離れて外国の地に行くことで日本を見つめ直し、日本人であることを意識するということはよくある。それと同じように宇宙に出ることで地球を強く意識し、地球人であることの自覚を持つようになるはずである。今後ますます地球規模の視野で考え、取り組まなければならない問題が増えてくる。
温暖化をはじめとする環境問題に特にそれが顕著である。「かけがえのない地球」「宇宙船地球号」という認識を広めていくためにも宇宙開発は積極的に推進すべきだといえる。
恐るべき隣人・北朝鮮
2002.10.08
「恐るべき隣人・北朝鮮」
ついに拉致の犯行を認めた北朝鮮。この無法国家といかにつきあうべきなのか。
まったく恐ろしい隣人を持ったものである。北朝鮮のことだ。9月17日に小泉首相が訪朝した時、金正日総書記は日本人を拉致したことをついに認めた。しかもそのうち8人はすでに死亡したという。これでこの国の本質が「犯罪国家」「テロ国家」「人さらい国家」であることが白日の下にさらされることになった。
実のところ北朝鮮が異常な国だということは以前から周知の事実だった。鉄のカーテンに覆われた謎多い国とはいえ、亡命者の証言やこれまでの国際社会での振る舞いからして、どういう国かということはだいたい分かってはいた。拉致被害にあったのも日本人だけでなく韓国人やレバノン人にまで広がっていることも判明していた。 それでも実際に北朝鮮が犯行を認めたことの衝撃は計り知れないほど大きい。今までの日朝交渉で日本側が拉致問題に触れるだけで席を蹴って退出していたのは一体何だったのか。実際に拉致していたにもかかわらず、よくそういう態度をとってこれたものだと思う。 まったく日本を愚弄した姿勢だと言わざるをえない。まして死亡者の多さやその年齢の若さは北朝鮮という国への疑念を強く抱かせる。ガス中毒死、交通事故死、溺死、自殺、心臓病死、あげくの果ては墓地は洪水で流出などという北朝鮮側の説明に納得しろという方が無理である。
広く世界に目を向ければ国家機関による拉致が他にまったくないわけではない。日本が舞台になったものとしては韓国中央情報部による1973年の金大中事件が有名である。イスラエルはナチスによるユダヤ人虐殺の責任者アイヒマンを亡命先のアルゼンチンから拉致した。19世紀末には清朝がロンドンで反政府活動を行なっていた孫文を拉致しようとして未遂に終わったこともある。こうした事件を正当化することはできない。だが北朝鮮による今回の犯行はこれらの前例とも違う異常な事件である。 従来の拉致というのは反政府活動家や当該政府にとって好ましからざる人物を誘拐したというものである。事の是非は別としてまだ理解可能な犯罪といえる。それに対し北朝鮮による拉致の被害者たちは反北朝鮮の活動をしていたわけでも何でもない。たまたま海岸にいた普通の人たちを海の向こうに連れ去ったのである。そんな国が現在のこの地球上に存在してよいのだろうか。
だが現実にそういう国が存在するのである。しかも日本と海一つ隔てて向かい合っている。だからといって引っ越すというわけにもいかない。我々としてはこの無法国家とどうやって付き合っていくかを否応なく考えざるをえない。北朝鮮との関係の基本は「対話」と「抑止」を二本柱とすべきである。あたりまえのようだがこれが重要である。俗な言葉でいえばアメとムチを両方用意するということである。あえて対話を拒むことはない。対話によって北朝鮮を国際社会の一員に迎え入れられるのであればそれが最善だからである。しかし「話せば分かる」というような生やさしい相手でもない。日米韓の連携を密にして毅然とした態度を示すことも必要である。
ここで難しいのが「対話」と「抑止」のバランスである。その点、これまでの対北政策は対話に軸足を置きすぎていたのではないか。つまりアメを与えることに傾斜していた感がある。日朝の国交正常化交渉は1991年に始まった。この交渉が中断するたびにコメ支援などを実施して、対話再開の機運を醸成してきた。結局6回のコメ支援が行なわれている。しかしこうした支援は北の姿勢を軟化させることにつながらなかった。 それどころか待っていたのはテポドンの発射であり、拉致問題での梨のつぶての回答だった。いわば北朝鮮は日本から支援を食い逃げしたのである。
北への宥和的な姿勢が変化したのは小泉内閣が誕生してからである。小泉首相は一貫して「拉致問題の解決なくして国交正常化なし」と言い続けた。安易な妥協はしないという姿勢を鮮明にしたわけである。今回まがりなりにも北朝鮮が従来の姿勢を転換しつつあるとすれば、こうした毅然とした外交姿勢があってのことだといえる。
ここでもう一度、従来の外交姿勢を反省してみる必要がある。もちろんこれは外務省の姿勢を問い直さなければならないということである。だが問題を外務省の責任だけに矮小化してはいけない。政治家やマスコミも含んだ国全体の問題と考える必要があるだろう。むしろ対北朝鮮外交を歪めてきたのは政党であり政治家だったといえる。北に擦り寄るような姿勢をとり続けたのは政治家の訪朝団だったのである。その最たるものが1990年の金丸信・元副総理率いるところの自民党・社会党の訪朝団だった。当時、北朝鮮は日本人船員2名を7年間にわたって不当に抑留していた。金丸氏らの訪問を機に2名は解放されることになるが、その時に小沢一郎・自民党幹事長、土井たか子・社会党委員長は「深い感謝の意」を表わす礼状を北朝鮮側に手渡している。不当な抑留に感謝するというのはどういうことだろうか。
ましてこの時は、戦後45年間についても日本が謝罪し償うことを約束をしている。戦前ならばいざ知らず戦後、日本が北朝鮮に被害を与えたということはない。むしろ被害者は日本側である。賠償するとすれば北朝鮮のはずである。こうしたおかしな交渉を議員外交の名のもとに政治家が行なってきたことは大きな失態といえる。
いま求められているのは抑止にしっかりと足場を持った交渉である。今から北朝鮮に言わなければならないことは山ほどある。拉致被害者の安否についてのさらなる情報提供、他に拉致されたと見られる人たちの安否、核開発の中止、ミサイル配備の撤去、通常兵力の削減、工作船の目的などどれをとっても重要なことである。それだけにこれらのことを主張する場が必要となってくる。話し合うのはよい。
だが言うべきことを言うという大原則を忘れてはならない。日本側の主張が通らないうちにあわてて国交正常化を進める理由はない。
実はこれは多くの国民の声でもある。小泉訪朝直後に朝日新聞が行なった世論調査では「北朝鮮と国交を結ぶ方がよい」とする人が59%、「そうは思わない」が29%となっている。だが選択肢に「(国交を)正常化すべきだが急ぐ必要はない」が加えられた読売新聞の調査では次のような結果になっている。
・できるだけ早く国交を正常化すべきだ 20.5%
・正常化すべきだが急ぐ必要はない 68.4%
・正常化する必要はない 5.5%
・答えない 5.7%
交渉して日本の主張をしっかりとすべきだが、安易な妥協はしてほしくないというのが世論の大勢だといえる。
北朝鮮という国との交渉では甘い幻想は禁物である。2年前に初の南北首脳会談が行なわれた時、これで朝鮮半島は敵対から和解への新時代に入ったという分析があった。だが実際はそこでの約束のほとんどは守られていない。北朝鮮が変化したという確証はまだない。ソ連が脅威でなくなったのは共産党一党独裁という体制そのものが変化したからである。 これに対し北朝鮮の独裁体制に変化は見られない。相も変わらず金正日の独裁体制が続いている。
もちろんペレストロイカもグラスノスチ(情報公開)も無縁なのである。国民は自国が犯罪国家であることなど知らされていない。それどころか北朝鮮は内外使い分けた勝手な宣伝を今なお続けている。こういう国との交渉は最大限慎重でなければならない。対話は行なうべきである。だが対話を請い願うことがあってはならない。まして支援などが先走ってはならないのである。
『一つの中国』は正しいか
2002.09.16
『一つの中国』は正しいか
一つの中国はフィクションである!日中関係の本質を衝く話題作。毎日新聞に掲載。
目下最大の外交上の話題といえば小泉首相の北朝鮮訪問だろう。電撃的な発表は大きな驚きをもって迎えられた。日本政府はこの北朝鮮と1991年以来国交正常化交渉を続けている。 北朝鮮はしばしば日本が国交を持たないほとんど唯一の国という呼び方をされる。しかし同じ東アジアにもう一つ日本が国交を持たない「国」が存在している。しかもこの「国」とは正常化交渉さえ行なわれることがない。それが台湾である。 台湾の人口は北朝鮮とほぼ同じ、経済力はタイやインドネシアをしのいでいる。これほど大きな存在であるにもかかわらず日本政府は国とは認めていない。政治的には存在しないかのように扱っているのだ。
私は今年の1月から外務大臣政務官をつとめていたが、この現状はあまりにも不自然だと考えた。そこで今夏政府の一員としての台湾訪問を希望した。残念ながらこれは外務省内で認められなかった。外交の根幹にかかわる方針で意見が違うにもかかわらず、ただ職に恋々とするわけにもいかない。結局先月末に政務官の職を辞することとした。
なぜ日本政府は台湾を認めないのか。なぜ私の訪台は認められなかったのだろうか。理由は実に簡単である。中国が怒るというだけのことである。中国は自国と国交を結ぶ国に対し、台湾を認めないように要求している。台湾はあくまでも自国の領土の一部だという建て前を堅持しているからである。いわゆる「一つの中国」という主張である。日本政府も1972年の日中共同声明でそうした中国の立場を「十分理解し、尊重」することを約束している。
だがそれから30年経ったいま、この見直しも必要ではないだろうか。なにしろ中国が一つだというのは現時点ではまったくのフィクションなのである。現にこの50年以上、中国と台湾は別々の道を歩んでいる。このフィクションに中国が固執している点にこそ東アジアの不安定要因がある。もちろん中国が将来の目標として統一を掲げるのは自由である。しかし日本など他国に対してまで「一つの中国を認めろ」と強要してくるとなると話は別になってくる。そして現実の中国は他国に「一つの中国」論を押しつけている。日本の選択肢として中国・台湾の双方と友好親善を深めるという道があって然るべきである。これを認めないと中国が言うのは行き過ぎといわざるをえない。
さらに中国は台湾への武力行使を時折ほのめかす。「一つの中国」という虚構を軍事力で維持しようとしているようにみえる。まず日本政府としては中国に対し「一つの中国」の押しつけをやめるように働きかけるべきである。武力行使の放棄を強く迫るのも当然である。日中関係は大切である。 だがすべて中国の顔色をうかがい遠慮をする必要もない。多額のODAを供与している以上、主張すべきことを主張するのは当然である。
外務省は対中外交のあり方について先例にとらわれず、幅広い議論をすべき時にきている。これは担当部局内だけでの狭い討議に終わらせてはならない。開かれた議論を行なうことこそ本当の外務省改革のはずである。鈴木宗男事件で反省すべきは北方領土のような重大事の意思決定が一部の人間の間でいつのまにか行なわれていたということである。外務省改革とは単に機構いじりをすることではない。外務省の体質そのものを変えていくことなのだから。
『台湾訪問を希望』との報道について
2002.08.12
『台湾訪問を希望』との報道について
このままでいいのか日本外交。抗議のため外務大臣政務官を辞任する直前に書いた憂国の論文。
私が台湾訪問を希望したということが報道されております。この件について多くの問い合わせをいただいていますので自分自身の考えを述べておきたいと思います。
私が外務大臣政務官として今夏に台湾を訪問することを企図し、それが外務省内で却下されたというのは事実です。まず訪台の狙いについて記したいと思います。台湾は日本にとって地理的にも近接した極めて重要な隣人です。経済関係の深さはいうまでもありません。さらに90年代に入り台湾の民主化は大いに進展し、自由や民主主義を奉じるという点でも我が国と共通の価値観をもっています。こうした台湾との関係を深めるというのはごく自然なことといえます。 時あたかも今年は日中国交正常化30周年にあたります。これは裏を返せば日本と台湾が断交してから30年ということに他なりません。正規の外交関係がないとはいえ、重要なパートナーとして歩んでいくという日本の意思を示すためにも外務省の一員として訪問するのは時宜を得たことだと考えたのです。
外務省には現在、大臣の下に副大臣二名、大臣政務官が三名おり、いずれも国会議員が勤めています。三名の政務官はそれぞれ担当地域を受け持つ形を取っています。具体的にいえば今村雅弘政務官が南北アメリカとアフリカ・南西アジア、松浪健四郎政務官が中東・中央アジア・ヨーロッパ、そして私が東アジア・ロシア・オセアニアとなっております。つまり中国・台湾は私の担当ということになります。それだけに自分が行くことがまさに政務官在任中の使命であると思ったわけです。
台湾を訪問すると中国が反発するのではないかと懸念する人がいます。日中関係が大切だということは言うまでもありません。しかしそれが台湾の切り捨ての上に立脚するものであってはならないのです。 台湾は人口2000万を超え、経済力もフィリピンやマレーシアを大きく上回る規模を誇っています。台湾という実態が現実に存在するにもかかわらず、あたかも存在しないかのように扱うことが正しい日本外交のあり方とは思えません。中国との関係は大切にしつつ、同時に台湾とも親善を進めるというのがあるべき姿です。 かつてドイツは東西に分裂していました。日本は西ドイツとは同じ自由主義陣営の国として友好関係にありました。しかし同時に東ドイツともきちんと外交関係を樹立していました。 日本政府の人間が東ドイツを訪問するからといって西ドイツが抗議するなどということはなかったのです。中国にもそうした寛容の姿勢を求めたいものです。
朝鮮半島も分断状況にあります。日本と韓国は1965年以来、外交関係を発展させています。その一方、日本政府は北朝鮮とも国交正常化交渉を続けています。しかもその北朝鮮は日本人を拉致し、ミサイルを発射し、核開発の疑惑まであるような国です。そういう国とでさえ外交的な接触をしているのです。これに対し台湾は拉致事件を起こしているわけでもなければ、ミサイルを撃ってきたわけでもありません。どうしてその台湾と政府レベルの接触をしてはならないのでしょうか。
もし中国が反発するというのであれば、そういう中国に対してこそ毅然として日本の言い分を主張すべきなのです。東西両ドイツと仲良くしていたように、台湾海峡の両岸とも友好関係を構築することが大切なのです。少なくとも台湾と友誼を結ぶことを中国側にとやかく言われる筋合いのものではありません。
政務官が台湾を訪問するとなればこれまでの日中・日台関係の転機となりうべき事態です。 それだけに台湾訪問に対し反対する意見があるのは当然でしょう。賛否両論があるのは世の常だからです。しかしそれならば訪台の可否についてしっかりと議論を行なうべきなのです。外務省では省議と呼ばれる幹部会があります。私は省議を招集し訪台問題をそこでの議題にすることを川口順子外相に求めました。残念ながら省議の開催は見送られそうな雰囲気です。省議による議論のないままに訪台拒否という結論だけが出されているのが実情です。本来、重要な問題であればあるほど徹底した議論を尽くすべきではないでしょうか。一片の決裁書によってこうした重大事が否決されるというのは得心がいきません。 私としてはあくまでも省議という公式の場で十分な議論を行なうことを求めているところです。
実を言えば過去に政府要人が台湾を訪問した例は皆無ではありません。近い例を取れば、昨年8月には厚生労働政務官だった佐藤勉衆議院議員が訪問し、今年1月には古屋圭司経済産業副大臣が葬儀への出席を名目に訪台しています。そうした中で何故外務省の場合は台湾に訪問できないのでしょうか。こうしたことをしっかりと議論するためにも省議が必要になってくると思います。
今、外務省改革ということが盛んに言われています。その目玉として大使への民間人の登用や組織改編など様々なことがあげられています。これらはもちろん大切なことです。しかし外務省改革という時に日本外交のあり方そのものを問い直すことは避けて通れません。本当に大切なのは外交改革なのです。そのためには政策についての徹底した討論が必要です。議論を封殺してしまっては改革の旗印が泣こうというものです。とりわけ中国関係については国民は高い関心を持っています。瀋陽総領事館事件の対応、対中ODAの必要性などは十分に検証しなければなりません。そうした一環として台湾訪問も闊達な議論が求められるところです。
「訪台に政務官としての進退をかけている」との報道もありました。現在政務官という政府の一員である以上、私がまず第一になすべきことは政府の方針に自分の意向を反映させるべく最大限の努力を傾けることだと思っています。そのためにも省議を開催し、訴えていきたいという意向を持っています。しかし努力はしたが、万策尽き果てたということもありえます。現にいまのところ台湾訪問は却下され、省議の開催さえ拒否されています。自説がまったく反映されないということであれば、やはりその政府の職に止まっていることはできないと思っております。自らの信念に反してまで政務官という職に恋々とするつもりはありません。
最後に誤解のないように付け加えておけば、私自身は川口外務大臣に対しては個人的には常に敬意を持ち続けております。僣越ながら強く親近感も抱いています。それは今なおまったく変わりありません。ただ残念ながら今回の一件についての考え方が違うというだけのことです。まずは意見の相違を埋めるべく努力をし、訪台を実現させたいと考えております。
今はまだ日台間に政府関係者の自由な往来がありません。しかし制約なく往来できる日がそう遠くない将来にくると信じています。またそうなるべきなのです。今回の行動がそのための第一歩になればと考えています。多くの方々に心情をご理解いただければ幸いに存じます。
あくまでも中国には陳謝を要求すべし (続・瀋陽総領事館事件)
2002.05.24
あくまでも中国には陳謝を要求すべし (続・瀋陽総領事館事件)
内外の注目を集めていた瀋陽総領事館事件に大きな転機が訪れた。中国武装警察によって連行された5名の北朝鮮人は中国から出国し、マニラ経由でソウルに到着した。亡命を求めていた彼らの希望が満たされたことをまずは歓迎したい。今回考えられる最悪の事態は5人が北朝鮮に送還されることだった。また中国官憲によって長期間拘留されることも望ましくない。結果として一家全員が自由世界に脱出できたことは良かったと思う。特に日本総領事館は庇護を求めてきた人を助けることができなかった。このまま彼らが非人道的な取り扱いを受ければ悔いを千載に残すところだった。その点でも出国できたことは喜ばしい。
だがこの問題はこれで終わりではない。一件落着という気運があるとすればそれは大きな誤りである。中国による国際法違反という重大問題が解決していないからである。この事件の本質は中国武装警察が無断で日本総領事館に侵入したことなのである。これは領事館の不可侵を定めたウィーン条約第31条に明らかに違反している。ところが中国側はいまだに謝罪もなければ責任さえ認めていない。この点を曖昧にしたままの幕引きは許されない。日本政府としてあくまでも中国に謝罪を要求し続ける必要がある。
ちなみに中国側は日本が警官の立ち入りに同意したと言い張っている。同意があったのだから違法性はなかったという理屈である。もちろん日本側が同意を与えた事実はない。だが百歩、いや千歩譲って中国の主張に一分の理があるとしよう。それでも中国が国際法違反を犯したという罪は免れないのである。仮に中国側の主張通り日本の副領事が同意を与えていたとしても、総領事館への立ち入りは認められることではない。ウィーン条約は「領事機関の長」の同意が必要だとしている。ちなみに瀋陽総領事館の場合は、総領事が長であり、その下に4人の領事、4人の副領事がいた。下位者である副領事が「入っていい」と言おうが言うまいが、総領事が同意していない以上、不法侵入であることに変わりはない。現場の邦人職員に恥ずべき行ないが多かったのは事実である。彼らの愚行は正当化しえない。しかしだからといって中国側の行為が正しいということにはならないのである。
中国の国際法違反は疑問の余地がない。ところが中国は謝るどころかかえって日本に対する批判を強めている。「中国の国際的イメージを悪化させた」と言い出してきた。まったく筋違いの批判である。イメージを悪化させるようなことをしているのは中国自身である。庇護を求める婦女子を力まかせに領事館から引きずりだしたのは中国の官憲である。他国の領事館に無許可で乱入したのも同国である。自らが国際的信用を失墜させることをしておきながら他者に責任をなすりつけることは許されない。
こうした問題では理非曲直を明らかにする必要がある。だからこそ日本政府は事件発生後まもなく5人の身柄引き渡しや中国の陳謝などを中国側に強く申し入れた。だがその後の政府の発言を注視すると微妙な変化が見られる。これらの要求を正面きって主張することを徐々に避けるようになってきたのである。まず身柄引き渡しの請求を事実上取り下げた。これはまあいい。国際法上は5人とも日本側に引き渡されるのが一番筋が通っている。だがあまりこの部分に固執すると拘束がいつまでも続くことになりかねなかった。庇護を求めてきた人を救うという人道的な観点からやむをえなかったと思う。
問題なのはいつの間にか陳謝のことまで触れなくなってきていることである。陳謝というのは当然すぎるほど当然の要求である。実は私個人は陳謝だけでは不十分だと考えている。国際法を犯した武装警官の処罰も中国に求めるべきだと訴えてきた。だが現時点の政府首脳の発言は武装警官の処罰どころか陳謝までも直接求めてはいない。実はこうした姿勢は理解できなくもない。5人が中国当局に拘禁され、事実上「人質」になっていたからである。「5人の安全確保のためには中国を刺激することは得策ではない」という意見も一定の説得力を持っていた。 だがついに5人は出国した。これで何のためらいもなく、主張すべきことを堂々と主張できるはずである。いまこそ再び陳謝要求を前面に打ち出すべき時である。
問題解決のために大局的見地から冷静に対処すべきだというという声もある。それはまったくもってその通りである。だがもしそれが“日中友好のためには些事に構うな。瀋陽事件はもう棚上げにしろ”という意味だとすれば賛成しかねる。私はむしろ大局的な見地から今回はあくまでも陳謝要求をすべきだと考えている。これまでの日中関係はとかく言うべきことを言わなかった。ここでそれを軟弱外交・弱腰外交と呼ぶことはしない。情緒的なレッテル貼りは健全な論議を損なうことが多いと思うからである。だがやはり日本の対中国外交に反省すべき点が多かったことは事実である。過ちは改めなければならない。
中国はいまや軍事大国である。東アジアの大きな不安定要因でもある。とりわけこの国が台湾への武力行使をほのめかすことは地域の安全保障上看過しえない。こうした中、中国に対し甘いことを言っていれば良いという時代は過ぎ去った。必要ならば苦言も呈していかなければならない。対中外交そのものを見直す必要がある。今回の事件はそのよい機会である。そのためにもあくまでも陳謝を求め続ける意味があるのである。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月