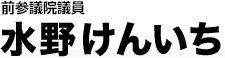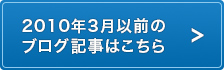- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
ポスター貼り
2010.06.20
「組織なし・カネなし」の「みんなの党」が選挙戦を戦う上で、悩ましい問題になっているのが「ポスター貼り」です。
ここでいう「ポスター貼り」というのは選挙期間中に公営掲示板に貼るポスターのことです。
公営掲示板には番号がふってあり、仮に5人が立候補すれば公示日の朝、抽選で各候補が1~5番いずれかの番号が割り振られます。
3番が割り振られた候補者は公営掲示板の3番の部分にポスターを張るわけですが、この掲示板の数は全県に1万1千か所余り・・。途方もない数です。
参議院の選挙戦は17日間ありますが、開始されて数日経ってもその番号だけが空白になっているというのではみっともないこと、この上ありません。
それだけにどの陣営も番号が決まると、できれば午前中にも貼ろうとして努力します。
組織のある政党はその点は楽です。労組や政党支部の組織に頼めば何とかなるからです。
「みんなの党」はそうした組織がありません。「組織なし、カネなし、しかし志だけはある」というのが「みんなの党」ですが、志だけではポスターは貼り終わらないので、多くのボランティアが欲しいところです。
お願いできれば連絡先は、
電話 043-463-2400
FAX 043-463-0475
メールでも結構です
政策ビラ
2010.06.19
選挙に立候補する予定の人は自分の政策や考えを有権者によく知ってもらう必要があります。そこで様々な方法で政策をアピールします。
もっとも現実には「政策を訴える」などという綺麗事だけでなく、まず知名度アップに力を注ぐということが多くあります。その典型が宣伝カーです。政策を真面目に訴える宣伝カーは稀ですが、名前を連呼する宣伝カーはよく見ます。
最近流行の戦術が候補予定者が自転車に旗を立てて回ることです。自転車に乗ったからといって政策を訴えることになるはずもありませんが、知名度を上げるにはある程度有効なのでしょう(やっている人は有権者と同じ目線で触れ合えるなど理屈はつけますが・・)。
さて政策を訴える王道は、人と会って話をすること、演説、ビラでしょう。最近はインターネットという手法もあります。中でも政策ビラはいろいろな場所で使えますし、ある程度まとまった内容も述べられるので重要な手段となります。
政治関係者には「どうせ文字なんか読まないから、写真や漫画を多くしないと駄目」などという人もいますが、それはちょっと有権者を馬鹿にしすぎかと思います。読まないのは読むに値しない文章だからで、読ませるビラを作るべく努力すべきでしょう。
ビラの天敵は雨です。雨が降っていると配布もしにくいし、湿気でビラが「くにゃ」となりますし、通行人も傘を持っているので受け取らないし・・と良いことがありません。
つまり梅雨こそビラ配布受難の季節といえます。そんな中ですが一人でも多くの人に政策を伝えるべく頑張っていきます。
県議会
2010.06.19
クイズです。「55vs20vsゼロ」とは何でしょうか。
答えは千葉県議会の「自民党vs民主党vsみんなの党」の勢力図です。
千葉県議会の定数は95。現在5名の欠員がいるので実際には90名が在職しています。
その勢力図は以下の通りです。
自民党 55人
民主党 20人
公明党 7人
共産党 4人
市民ネットなど 4人
みんなの党 0人
前回の県議会議員選挙は3年前の4月に行なわれています。「みんなの党」の結成は昨年8月です。ですから前回選挙の時には「みんなの党」は存在さえしていませんでした。
選挙ではよく「組織固め」という言葉が使われます。系列地方議員や業界団体の組織をフル稼働させることなどを指します。
そういう見方からすれば「55vs20vsゼロ」の中で参議院選を戦うのは無謀かもしれません。
しかし国民の声をいま一番体現できるのは「みんなの党」だ、という自負を持っています。
その中で果敢に挑戦してきたいと思っています。
手ごたえ
2010.06.19
街頭演説などの活動をしていると、記者の方からよく「手ごたえはどうですか」と聞かれます。今まで何回か立候補経験がありますが、正直なところよく分かりません。というか「手ごたえ」という曖昧なものは、あまり信じていないというのが本当のところです。
確かに「頑張って」とか声をかけてくれる人はいます。しかし逆風の時でも「頑張れ」という人はいます。例えば自民党は大敗した昨年の総選挙でも全国で比例で26%の票はとっています。ですからそうした大逆風でも自民党に対して「頑張れ」と言う人がいても、全然不思議ではありません。
(逆に民主党も大敗した2005年の郵政選挙で比例区では30%の票を獲得している)
結局、「頑張って」という人が何人かいたからといって(それはそれでありがたいですが)、「手ごたえは良い」と思うととんだ勘違いになります。世の中の逆風が止んでいることを意味しているわけではないからです。
他に「手ごたえ」の尺度になるものとして、次のようなものが挙げられます。
・手を振ってくれる人が多いか少ないか
・チラシの受け取り具合が多いか少ないか
こうしたことを気にする候補者も多いようですが、私自身は客観的な世論調査ならともかく、あまりそうした体感は信じないというのは、さっき述べた通りです。
ここまでそう書いておきながら平気で矛盾することを言うようですが、いま体感で「みんなの党」への期待が非常に高い感じがします。街頭演説などをしていると特にそう感じます。
もしかすると「みんなの党」への期待というよりも民主党・自民党への幻滅の裏返しだけなのかもしれませんが「期待できるのはみんなの党だけ」という雰囲気があると思います。
そうした声に応えられるべくしっかりと気を引き締めて選挙に臨みたいと考えています。
図書館
2010.06.19
私が中学高校生の頃、学校(私の通っていた学校は中高一貫だった)から歩いて数分のところに都立中央図書館という図書館がありました。
ここは16歳以上しか入館できないという年齢制限があったので中学生は入れませんでした。それだけに中学生の時、同級生が「高校生のふりをして入った」などというのが一種の武勇伝のようになったりしていました。いま思うと可愛い武勇伝です。
また「○○先輩は中央図書館で△△(女子高の名前)の彼女と一緒に机並べてたぞ」などというのが話題になったりしました。これまたいま振り返ると可愛らしい日々だった気もします(ちなみにうちの学校は男子校でした)。
さて国会議事堂の傍には国立国会図書館があります。こちらは18歳以上(昔は20歳以上でした)でないと入館できません。
国会図書館には「調査及び立法考査局」という部門があり、ここは国会議員のために資料集めをしたり、調査研究をしてくれます。国会議員からすればありがたい存在です。
米国議会の図書館にもCRS(コングレショナル・リサーチ・サービス)という同様の部署があり、スタッフ数などは日本の国会図書館よりもずっと多くいます。
確かにこうした機能を持つ部署があることには意味があります。議員が政策を立案にしようにも資料集めなどを全部自分でやるというのでは効率が悪くなります。
資料も役所に依存するだけでは、その役所の都合のよいデータしか出してきません。だからこそ国会図書館という中立機関が必要になってきます。
問題は議員がこうした国会図書館の機能を使いこなせるかどうかです。役職だけを欲しがって政策立案には無縁という政治家には、国会図書館のこの機能は無用です。
そんな議員ばかりになっては国会図書館も単なる宝の持ち腐れです。しっかりと利用して、よりよい政策作りをしていきたいと思います。
注)今回、この原稿を書くために調べてみたら現在は都立中央図書館の入館には年齢制限はなくなっているとのことでした。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月