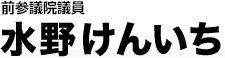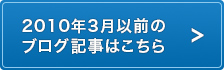- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
一票の格差
2010.04.19
千葉県の人口は600万人、全国最少の鳥取県は60万人。10倍の差があります。それでいて参議院の定数は千葉県は3で、鳥取県は1。
人口比(有権者比も大体同じ)から言えば鳥取県が定数1ならば、千葉県は10あってもおかしくないところですが・・(千葉県の定数を10にしろと言っているわけではありません。議員数はむしろ減らす方向に進むべきですから。念のため)。
これがいわゆる一票の格差です。衆議院にも一票の格差はありますが、参議院はさらに極端です。一票の格差を完全に無くすことは難しいにしても少なくとも2倍以内に抑えるのが普通でしょう。
ある人が他の人の2倍もの票を持っているというのは常識で考えておかしいからです。堅く言えば「法の下の平等」に反します。こうした当たり前の感覚も国政に反映させていきたいと思います。
マニフェスト
2010.04.18
「マニフェスト」という言葉が頻繁に使われるようになったのは2003年総選挙の頃からだと思います。もちろん以前から「公約」という言葉はありました。じゃあどこが違うのでしょうか。
マニフェスト選挙の提唱者(北川正恭・三重県知事ら)が当時言っていたのが、公約が抽象的なスローガン集なのに対してマニフェストは数値目標・期限・財源を明示するものだということでした。
「福祉を充実させます」「地域発展につとめます」というだけでは抽象的なので、「2年以内に保育所待機児童をゼロにする」と具体的に書くのがマニフェストだということになります。そうすれば後になって達成度合いを検証できるというわけです。
つまりマニフェストは作成も重要ですが、実現しているかどうかの検証もそれに劣らず重要といえます。
もっとも今の民主党政権を見ていると細かく検証しなくてもマニフェスト違反に満ち満ちていることは明白です。高速道路無料化、ガソリン税の暫定税率廃止、天下り禁止...次々と反故にされています。
そういえば昨年の総選挙前、民主党は「政権交代」のスローガン入りの鳩山由紀夫さんのポスターをいたるところに貼っていました。実は総選挙後は「政権交代」の文字を「公約実行」に差し替えただけの同様のポスターを作成しています。もちろん鳩山さんの顔写真は同じです。
ところがこの「公約実行」のポスターは作ったもののほとんど街で見かけません。「実行していないじゃないか」と突っ込まれるから恥ずかしくて貼れないんでしょうねえ。
今どきの若い者
2010.04.17
「今どきの若い者は」と言い出すようになったら精神的に老けてきた証拠だという説があります。それにしてもこの「今どきの・・」という言葉はよく耳にします。ベテランスポーツ選手(といっても30代くらい)が「自分たちが新人の頃はもっとハングリー精神で練習したのに今どきの若い奴は」と言う時もあれば、テレビを見ていたら高校生が「今どきの中学生は」と言ってたので「ありゃ」と思ったこともあります。古代エジプトの象形文字を解読したら「近頃の若いもんは」ということが書いてあったといいますから、このセリフは古今東西あまねく使われているのでしょう。
昔を懐古するのは人間の常なので悪いとは思いません。しかし新しいものをただ毛嫌いしては進歩もありません。先輩には敬意を払い伝統は尊重しつつ、若い人の声にもきちんと耳を傾け旧弊を打破する柔軟さが大切です。
そういえば政界にもいます。「近頃の若手議員は勝手なことを言いすぎる。俺たちが若手だった頃は派閥の長が右といったら右、左といったら左で一糸乱れなかったんだ」という人が。こういう派閥政治家こそ老害なので早く退場してもらいたいものです。それでもこうした“一致団結箱弁当”的な政治家は減ってきたと思っていたらまだまだいました。しかも政権与党の最大実力者に。幹事長が白といったら黒いものも白といわなきゃ許さないという雰囲気を作っている人が・・。
ブログ開設
2010.04.17
ブログを開始することにしました。これまでホームページには論文やチラシの文章は多く掲載しましたが、ブログを書くのは初めてです。以前から人には「ホームページは更新が命なんだからブログでもやった方が良いよ」とは言われていたんですけど、どうも億劫で・・。言い訳ばかりになりますが、毎日書くと「今日食べたラーメンはおいしかった」とか「雨なので憂鬱」とか後で振り返ると読むに堪えないくだらない内容ばかりになりそうなのも気が引けていた理由です。
それでもツイッタ―をやる政治家も増えている今、せめてブログで近況や考えを報告してみようと思いたちました。最低でも二日に一回は更新したいと思います。今後ともよろしくお願いします。
「脱官僚」は本当に進んでいるのか?
2010.01.15
「脱官僚」は本当に進んでいるのか?
〜「政治家主導の政策立案」を以前から唱えてきた水野賢一に聞いた〜
Q1 民主党政権のもとで「政治主導」「脱官僚」が叫ばれている現状をどうみますか?
水野 政策立案を官僚任せにするのではなく政治家が主導権を握るという方向は間違っていないと思います。選挙で選ばれた人間が政策を作り、責任も取るというのが民主主義の本来の姿だからです。それだけに現在、口先で脱官僚を唱えながら実際にはそれに反する動きが進んでいることには危惧を持っています。 例えば日本郵政の社長に「ミスター大蔵省」と呼ばれた元大物次官を起用したことはその典型です。また政治主導と言いながら小沢一郎幹事長が議員立法の制限を打ち出しているのも妙なことですね。
Q2 水野さんは衆議院議員時代に議員立法に力を尽くしましたね。
水野 国会議員というのは“立法府”の一員ですし、英語では“law maker”とも呼ばれています。つまり法律を作ることこそ本来の仕事です。「政府がやらないのであれば自ら立法する」という気概を持ってこそ立法府の一員だと思います。ですから議員立法の制限という小沢幹事長の方針は理解に苦しみます。政府提出の法案に対して賛成票を投じるだけならば、閣僚など要職以外の与党議員は単なる採決要員にすぎなくなってしまいます。
Q3 事業仕分けなど新しい試みに対してはどう考えますか。
水野 無駄を洗い出すという点では一定の評価はできると思います。長年続いてきた事業の中には「昔は意味があったが今では不要なもの」や「国ではなく地方自治体がやるべきもの」もあったからです。一方で問題点も浮き彫りになりました。「1時間程度の議論で正しい仕分けができるのか」「短期的なコストだけで判断してよいのか」という批判ももっともな点が多いので、やり方の改善は必要でしょう。
ただ最大の問題は官僚叩きに終始して、政治家が責任を引き受けようとしなかったことです。事業仕分けでは各省庁が出してきた概算要求に無駄がないかどうかに切り込んだわけですが、概算要求を行なった各省庁の最高責任者は大臣・副大臣・政務官といった政務三役、つまり民主党などの与党議員です。もし無駄な要求をしていたならば本当に責められるべきは彼らなのです。ところが仕分け人の矢面に立たされていたのは事務レベルの官僚ばかりでした。政治主導と言うならば批判や責任も自ら受けるという姿勢が求められます。
Q4 水野さんには本当の意味での政治主導を期待しています。
水野 ありがとうございます。国政の場で再び働けるように研鑽を重ねてまいります。
ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月