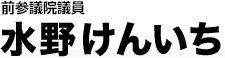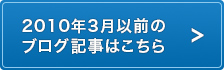渡辺喜美・みんなの党代表が5月30日(日)に千葉県に来訪されます。
街頭演説の予定は、
日時)5月30日12:45~
場所)JR柏駅東口デッキ
となっております。
一週間前の23日(日)にも渡辺代表は千葉市で街頭演説を行ないましたが、あいにく雨天でした。それでも多くの方が耳を傾けていただいたのは嬉しい限りです。
天気予報によれば30日は「曇り」。天候に恵まれることを祈念しつつ、一人でも多くの方々の来場を心待ちにしています。
- TOP >
- ブログアーカイブ
30日に渡辺代表来たる!
2010.05.28
尊敬する人(その1)
2010.05.27
前回のブログの続きです。マスコミからの調査票には、「尊敬する人は?」というのもあります。
多い回答は、
①歴史上の有名人(地元の有名人の場合もある)
②自分の政党・派閥の領袖
③身近な人
といったところでしょう。
①は坂本竜馬やガンジーといった具合で、新潟県の候補者が上杉謙信と回答するようなバージョンも結構あります。
②は昔に比べて最近は減っているような気がします。確かに民主党の人も「鳩山由紀夫」とは答えにくいでしょうし、自民党でも今どきこんなところで派閥の親分にゴマをすってもしょうがないでしょうし・・。
③は両親とか恩師ですが、恩師の名前を書いても一般の有権者には誰だか分らないので、政治家の回答としては不向きかもしれません。
じゃあ私は誰と書いているかって?。毎回「リンカーン」と回答していますが、実際には会ったことも話したこともない歴史上の人物が本当に尊敬に値する人なのかは100%は自信がないというのが本音です。
(尊敬する人〔その2〕に続きます)
座右の銘
2010.05.26
国政選挙が近づいてくるとマスコミ各社から候補者に「立候補予定者調査票」が渡されます。
生年月日、学歴、過去の選挙歴、事務所所在地などについて記入してくれというものです。
以上に加えて、質問項目に多くあるのが、「座右の銘は?」「尊敬する人は?」という問いです。
「座右の銘」について、他の政治家の回答を見ると「努力」とか「チャレンジ」といった分かりやすいものもありますし、一方で「信なくば立たず」のような漢語も人気が高いようです。
私の場合、「座右の銘」と言われても、ある言葉を日々反芻しながら暮らしているわけではないので、なかなか回答が難しいところです。
とはいえ「無し」と答えるのも素っ気ないので毎回「千万人と雖も吾往かん」と書くことにしています。
(せんまんにんといえどもわれゆかん、と読みます)
出典は『孟子』で“自分が正しいと思ったら例え敵が千万人いようとも自分の道を行く”という意味です。簡単にいえば信念を貫くということでしょう。
政治を志す以上、そういう政治家になりたいという思いはあります。ただ最近ちょっと考え直さなければいけないかなとも思います。
自分の勝手な思い込みや、単なる頑迷を「信念」と言い張る人も多く見るからです。しっかりとした自分の信念・理念は持ちつつ、他の意見への寛容さや柔軟さを忘れずに、常に我が身を省みるという謙虚さも大切にしたいと思います。
爽快感
2010.05.25
「みんなの党」から千葉選挙区で参議院選挙に出馬表明してから3週間余り。つまり「みんなの党」として街頭演説を始めてからそれだけ経つわけです。
私も自民党の衆議院議員として10年を過ごしましたので、街頭演説は今までにも何度もやっていますが、「みんなの党」として実施するのはきわめて爽快なものです。
国民の期待が高い政党なので反応が良いということもありますが、それ以上に自分自身の本心から喋ることができるという点です。
自民党時代、特にこの数年は、「今の自民党には問題があります。だから私たち若手が変えていくしかありません」というトーンになりがちでした。
それはそれで本心でしたが、心の中のどこかで「そうは言っても若手が頑張ったくらいで、そんなに簡単に変わるだろうか。動脈硬化を起こした今の自民党を変えるのは至難の業ではないだろうか」という思いも、少しあったのは事実です。
いわば迷いがありながら訴えていたわけです。
それに対して今は心おきなく自分の考えを言えます。これが爽快感の理由です。
そう思っていたら、敬愛する山内康一衆議院議員が昨年8月5日のブログで同じようなことを書いていました。
山内議員は昨年の総選挙直前に自民党を離党し、「みんなの党」の結成に参加しています。いわば離党の先輩です。
自民党内で改革派とされている人たちは大なり小なり似た思いを持っていると思います。
「みんなの党」が参議院選挙で躍進することで政界再編の波を起こし、自民党や民主党の良質な人たちが、自分たちの党に見切りをつけるはずみになればとも思います。
早起き
2010.05.24
今から1300年ほど前の唐の詩人・孟浩然(689~740)の詩に「春眠暁を覚えず」という一節があります。
春の眠りは心地よいので、夜明けにも気付かずにウトウトする、ということです。
私の場合、その春になって急に朝早く起きるようになりました。4月に参議院選出馬を表明したからです。
各候補予定者は朝、駅に立ち、通勤客などに訴えたり、チラシを撒いたりしますが、私も例外ではありません。
もちろん衆議院議員時代にも駅に立つことはありましたが、違いは選挙区の面積です。
参議院の選挙区は全県です。衆議院時代の選挙区が佐倉市、四街道市、八街市、千葉市若葉区だけだったのに比べると格段に広くなります。
佐倉市在住の私からすると、遠方の駅にも行く必要も出てきます。つまり以前よりも早起きになるわけです。
参議院選は真夏の予定。ということは「暁を覚えず」というほど朝寝坊できる日は、秋までなさそうです。
演説の適地
2010.05.23
お店を出す人が立地条件を考えるように、演説をする人も場所を考えます。
駅前の繁華街よりも人の少ないところから演説をやっていくという「川上作戦」(川の上流からやる、ということらしい)もあるようですが、普通は人の多いところこそ適地だと思うのが人情でしょう。
また地域によっては「ここは毎週月曜日は△△党、火曜日は××党が演説をするのが暗黙の紳士協定のようになっている」とか色々とあるようです。
私自身が衆議院選挙に出ていた千葉県9区のエリアでは「あそこは何曜日の何時にセールがあって人が集まる」とかがある程度は分かりますが、それ以外の地域だと、こうしたことがよく分からないというのが実情です。
「みんなの党」水野賢一を応援して下さる方々にお願いをいたします。こうした「演説の適地」の情報などをメールか何かで教えていただければ幸いです。
ご教示いただいたからといって、必ず行けるかといえば、日程の都合などで、難しい場合が非常に多いかとは思いますが、こうしたきめ細かな情報はあるに越したことはないので、よろしくお願いします。
来たる!渡辺喜美代表
2010.05.22
「みんなの党」の渡辺喜美代表が明日(23日)千葉県に来られます。
「地域主権型道州制国民協議会」が主催する「タウンミーティングin千葉」に元々参加される予定でしたが、千葉市まで来られるということで、このタウンミーティング終了後に、私と一緒の街頭演説活動も行なうことになりました。
街頭演説の予定は
日時)5月23日(日)午後5時頃
場所)千葉駅東口クリスタルドーム付近
となります。
なおそれに先立って行なわれる道州制についての「タウンミーティングin千葉」は私が主催するわけでなく、「地域主権型道州制国民協議会千葉市支部」が開催します。
こちらは午後2時からJR稲毛駅近くの「稲毛サティ4階文化ホール」で行なわれるそうです。参加費無料だということですが、申し込みなどについての問い合わせ先は、
電話 043-245-2090
FAX 043-245-2091
ということです。
午後5時頃のJR千葉駅での街頭演説では、私自身もマイクを通して、訴えていきたいと思います。
お時間がある方は足を止めていただければ、幸いに存じます。
事業仕分け
2010.05.21
人気急落の民主党ですが、事業仕分けだけはまだ期待が高いようです。
それだけに民主党としては今行なっている事業仕分け第2弾で支持率をアップさせようという思惑も持っているのでしょう。
5月5日のブログにも書いた通り、私は事業仕分けについて一定の評価はしています。しかし問題点も指摘しなければなりません。
事業仕分けは以下のような流れで進んできました。
平成21年11月・・第1弾(来年度予算についての仕分け)
平成22年 4月・・第2弾前半(独立行政法人について)
5月・・第2弾後半(公益法人について)
4月に行なわれた独立行政法人についての仕分けでは、36事業を「廃止」、50以上の事業を「縮減」という判定が下されました。
それだけ見ると頑張っているようですが、実は独立行政法人そのものは民主党政権が発足してから新たに6つも設立されているのです。
これを放置したまま一部の事業だけを削っても本丸に斬り込んだことにはなりません。こうしたことも国民に広く周知しておく必要もあると思います。
大隈重信は議員だったのか
2010.05.20
前の号で私の母校の創立者・大隈重信について触れました。
大隈重信が内閣総理大臣をはじめ要職をつとめたことは知られていますが、ある時、私はふと「大隈侯は国会議員(当時は帝国議会議員)をつとめたのかなあ」と思って調べてみました。
というのも現行憲法では内閣総理大臣は国会議員から選ぶ(参議院からでも可能だが、その例はない)ことになっていますが、戦前は首相が議員である必要はなかったからです。
調べてみると大隈重信が帝国議会議員をつとめたのは最晩年の6年だけでした。
それも侯爵に叙されたことに伴って貴族院議員に就任しただけのことであり、選挙で当選したというわけではありません。
大隈重信と一緒に銅像が国会内に立っている伊藤博文も貴族院議員をつとめただけ。板垣退助は議員歴はありません。
選挙の洗礼を経なくても国政の中枢に関わった方々に思いをはせると、選挙のことを常に気にしなければならない現代政治の渦中にいる身としてはちょっとうらやましい気もします。
もっとも選挙の苦労はしなくても文字通り命懸けの修羅場をくぐってきた人たちですから、それ以上の艱難辛苦をなめたのは間違いないでしょうが。
大隈重信の像
2010.05.19
早稲田大学卒業生の会を稲門会といいます。私も平成3年政経学部卒業生として佐倉稲門会の一員となっています。
早稲田大学の創設者といえば大隈重信です。早稲田大学キャンパスの中にある大隈重信の銅像は昭和7年に除幕され、大学の象徴ともいうべき存在として有名です。
大学内の銅像ほど有名ではありませんが、実は国会議事堂の中にも大隈重信像があります。
議事堂の一番高い部分は高さ65m(法隆寺の五重塔が31mなのでそれに比べても結構高い)ですが、その真下の部分に中央広間があります。
ここはちょうど衆議院部分と参議院部分の中間で、この広間の四隅には立憲政治の基礎を築いた明治の政治家3人―大隈重信、伊藤博文、板垣退助―の銅像が置かれています。
四隅に3人というと残る一隅は、といえば台座だけが置いてあって像はありません。その理由として以下のようなことが言われていますが定説はないようです。
①将来ここに像が立つような政治家が登場することを期待する
②政治は未完であるということを示している
③ここに像を立てると皇居に背中を向けてしまう形になる
④4人目の人選が難しかった
真相がいずこにあったのかは分かりませんが、①の説が一番きれいなような気もします。
まあ大隈重信たちは周りの人たちが「あの人は偉大だった」ということで銅像を建ててくれたのでしょうが、近くの独裁国家の首領様(金日成のこと)のように自分で自分の巨大な像を首都に立てるという神経はちょっと分かりませんねえ。
注)卒業生としては学校の創設者に敬意を表して「大隈重信侯」(侯爵だった)と書くべきかもしれませんが、歴史上の人物として敬称を略しました。
(以下、次号「大隈重信は議員だったのか」に続く)
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月