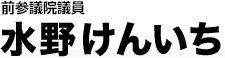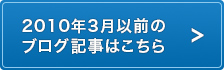- TOP >
- けんいちブログ
けんいちブログ
「原発の事故調査委員会の動き」
2011.10.31
原発の事故調査委員会の動き
~みんなの党も幹事会メンバーに~
東京電力福島第一原発の事故調査委員会を国会に置くことを定めた法律が昨日(10月30日)施行された。近々、事故調査委員会が発足することになる。
本日もその準備のための各党協議会が開催された。事故調査委員会は国会の中でも衆参の議院運営委員会の合同協議会の下に置かれる形になるので、私も参議院の議運理事としてこの各党協議会に参加した。
国会に置かれるといっても国会議員が調査委員になるわけではない。国会が民間有識者10名を委員として選ぶ。基本的にはその人たちが関係者から聞き取りをしたり、資料を提出させたりして事故原因や政府の事故対応などを調査・検証することになる。
実は政府の事故調査・検証委員会というのがすでに設置されており、6月から活動を始めている。「失敗学」を提唱している畑村洋太郎・東大名誉教授を委員長として、これまでに338人からヒアリングを実施したという。
今回、それに加えて国会にも事故調査委員会を設置したことになる。だからといって屋上屋を架すことにはならないと思う。両者にはいくつかの違いがある。例えば政府の事故調査・検証委員会は原則非公開だが、今度国会に設置される事故調査委員会は公開が原則となっている。
そうした違いもあるが、国会に設置する最大の意味は中立性・信頼度の問題だといえる。いま政府の事故対応が問われているのである。そうした中、政府に設置され、政府が人選を行なった委員会では「本当にきちんとした調査ができるのか」という疑念が拭いきれない。
もちろん政府の委員会も一生懸命に取り組んでいるのだろう。年末には中間報告をまとめるというが、有意義な報告書を出してくるのかもしれない。しかし中立性に疑念を持たれるだけでその報告書の価値は下がってしまう。まして今回の事故は国際社会も注視している。それだけに中立性・信頼性への疑念はできるだけ払拭しておきたい。しかもこれだけの大事故である。政府が自ら検証することを否定はしないが、違った眼で多角的に分析することも大切だと思う。
さて“国会に設置する”といっても、先に述べた通り調査を実施するのは10名の民間有識者である。では国会の役割は何なのか。費用負担はもちろんである。かかる経費は衆参両院が分担する。それ以外にも大きく分ければ二つある。
一つは委員の人選である。政府の委員会の場合、委員は政府が人選したが、こちらは国会が10名の民間有識者を選任する。衆参の議院運営委員会の合同協議会が、委員長と9名の委員を推薦して両院本会議の了承を得て任命される。それだけに一党一派に偏った人選は考えにくくなる。
もう一つは資料提出を拒む者がいた時など、何らかの強制力を発動しなければならない時である。その時は調査会は上部機関である衆参の議院運営委員会合同協議会に国政調査権を発動してくれと要請することになる。そうするとこの合同協議会が強制権をもって資料の提出を求めることができる。いわゆる国政調査権の発動である。ちょうど国会が強制力をもって証人喚問できるのと同じことである。ちなみに政府の事故調査・検証委員会にはその権限はない。
本日の各党協議会では合同協議会の構成などを決めた。衆参15名ずつの合計30名で、各党の割り当ては以下のように決まった。
衆議院 参議院
民主 9 8
自民 3 5
公明 1 1
みんな 0 1
共産 1 0
社民 1 0
合計 15 15
なお合同協議会の会長には衆議院議院運営委員長(現在、民主党)が、会長代理には参議院議院運営委員長(現在、自民党)がつく。
さらに30名全員で合同協議会の運営を決めるのは難しいので、その中に幹事会を設けることにして、構成を次のようにすることも決めた。
衆議院 参議院
民主 4 3
自民 2 2
公明 1 1
みんな 0 1
合計 7 7
cf.幹事会にはこの衆参7名ずつ以外に会長と会長代理が加わることになる。
cf.なお合同協議会も幹事会も正規の委員や幹事以外のオブザーバー参加の余地も残している。
今後、大きな焦点になるのが事故調査委員の人選である。こうした点でもみんなの党の意見を反映させられるように努めていきたい。
とりわけ事故調査委員会はベントの遅れなど直接的な事故対応を調査するだけでなく事故の遠因になった原子力村の馴れ合い体質などにもメスを入れると考えられる。こうした部分にも鋭く切り込めるような適任者を選んでいくことがまず第一である。
「袖ヶ浦市長選で党推薦候補が惜敗」
2011.10.31
袖ヶ浦市長選で党推薦候補が惜敗
~新人の渡辺薫さん、残念ながら届かず~
昨日、千葉県袖ヶ浦市長選挙の投開票があり、みんなの党が単独推薦した渡辺薫氏は次点に終わった。開票結果は以下の通りである。
当 出口清 10067 現 無
渡辺薫 8937 新 無(みんなの党推薦)
大森正行 6589 新 無
渡辺氏が当選すれば千葉県内で初のみんなの党推薦の市長が誕生するところだった。まして他党と相乗りでなく単独で推薦した候補の勝利となると全国でも珍しいことになる。
連日、袖ヶ浦入りして自ら自転車をこいで選挙応援した佐藤浩・党千葉県議団長をはじめとする党所属県議・市議や党関係者には頭が下がる。
言うまでもないが、渡辺氏の選挙運動に力を尽くしたのはみんなの党の関係者ばかりではない。地元の浜田靖一衆議院議員(自民党)をはじめとする自民党系市議の方々、党派にかかわらず渡辺氏を応援した心ある袖ヶ浦市民の方々の力は絶大だった。もちろん候補者本人や周りの人たちも必死の努力を積み重ねてきた。
cf.自民党系議員は大森候補の支持にまわった人たちもいたので、いわゆる保守分裂選挙の形になっていた。なお現職の出口候補は政党推薦は受けていなかったが東電労組出身で民主党系と目されていた。
残念ながら選挙結果はこうした努力を実らせるものにはならなかったが、渡辺氏に票を投じた方々の思いが、袖ヶ浦市のより良い未来のためにつながっていけばと思う。ともあれ候補者も奥様も本当にお疲れ様でした。
電力使用量のデータを隠すな(その1)
2011.10.30
電力使用量のデータを隠すな(その1)
~経済産業省は全面開示せよ~
10月27日の参議院環境委員会で質疑に立った。ここで追及した大きな柱が「経済産業省は各企業の電力使用量のデータを開示しろ」ということである。実は経済産業省は、どの会社のどの事業所が年間どれだけの電気を使ったかというデータを持っている。省エネ法という法律によって一定以上のエネルギーを使った事業所には、その使用量を報告する義務がかかっているからである。
問題はそのデータが十分に開示されていないことである。そこで開示せよと迫ったわけである。どのような答弁だったかを記す前に、なぜこのデータを公開すべきなのかについて触れておく。
今年8月に再生可能エネルギー買取り法が成立した。党内外の退陣圧力で瀬戸際に追い詰められていた菅直人首相が「退陣させたいならこの法案を成立させろ」と条件に挙げていたあの法律である。
この法律は政府が提出したが、国会審議の中で修正が加えられた。自民党が「この法律が成立すると電気料金が上がる。上がると電気を多量に使う会社は困る。だから多量に使う会社の電気代には配慮すべきだ」と主張したためである。
そこで「製造業で平均よりも8倍以上電気を使う企業の電気代は大幅に割り引く」ということになった。私は再生可能エネルギーの買取り制度には賛成だが、この修正は法案の改悪だと考えており、このブログでも7月28日に「後ろ向き修正」だと強く批判した。
cf.この法律については本ブログの7月28日、8月2日、8月30日の項でも触れている。
電気を多量に使う業界というのは電炉、化学、鋳造といった業界である。私はこうした特定業界を優遇する修正は不要だと考えるが、百歩譲って一定の配慮は必要だとしても「何で8倍なんだ」という疑問は出てくる。5倍でも10倍でもなく、なんで8倍で線を引くのかその根拠がさっぱり分からない。
続いて出てくる懸念は「いま平均よりも7倍使っている会社は、わざと電気を浪費して8倍まで使って大幅な軽減の適用を受けようとするのではないか」ということである。一方で国民に節電を呼びかけながら、一方で電力浪費につながる施策を許すわけにはいかない。
8倍が妥当なのかどうかを議論するためには現状のデータが必要である。例えば平均の7倍使用している会社がたくさんあるならば上の懸念はかなり深刻になる。逆にほとんどないならば杞憂に終わるかもしれない。そこで法案審議の時に私は次のように主張した。「こうした疑問や懸念を払拭するためには、どの企業がどれだけの電気を使っているのかのデータがないと議論できないではないか。少なくとも経済産業省が現在持っている電力使用量のデータは公開すべきではないか」。
それに対し海江田万里経済産業大臣(当時)は8月25日の委員会で「議論を深めるために資するものであれば、それはできるだけ出すようにということを役所に対して申し上げましたし、そういう姿勢で臨むということは今私から委員に対してお答えを申し上げます」と答弁した。
その言や良しである。ところが驚くことにそれから2か月経った今でも新たな公開はゼロである。これは何も新たに調査するという話ではない。それならばある程度時間がかかっても仕方がないだろう。しかしすでに持っている資料を公開するだけのことである。やろうと思えばすぐにでもできるはずだが、まったく前進がない。
そこで先日の環境委員会であらためて早期公開を迫った。その追及内容や、現在何社のデータが非公開になっているかなどについては、次回以降のブログで報告させていただきたい。
「横峯良郎議員の航空機クーポン券(その2)」
2011.10.28
横峯良郎議員の航空機クーポン券(その2)
~自ら申し出て疑惑解明に協力すべき~
10月25日のブログで横峯良郎議員(民主党)の航空機クーポン券の問題を取り上げた。実態のない「地方住所」を沖縄県に登録して、クーポン券を過大に貰っていたのではないかという疑惑である。
そこにも書いたが横峯議員は「月3往復の航空機クーポン券+JR無料パス」を貰っている。疑惑が浮上した後、鈴木政二・参議院議院運営委員長が同議員のクーポン券の使用実態を事務方から提出させた。クーポン券の使用状況は院に資料が残っているので、それを出させたわけである。こうした資料は「政治活動の自由」に関わるとして普通は非公開である。だが疑惑があるということで議運理事会の議論を受けて理事会メンバーには公開することになった。
私も理事の一人なので、それを目にしたが、横峯議員は平均すると月に8回ほど飛行機に乗っていることが分かった。月3往復ならば普通は6回までのはずである。それが約8回搭乗しているのは、遠距離に地方住所を登録して高額のクーポン券を受領しておいて、実際にはもっと短距離の区間を乗っているからである。
羽田~那覇で登録しておくと、一か月に貰えるクーポン券は24万5400円分になる。片道40900円で3往復という計算になる(金額は通常期と多客期で多少違うので、ここでは2010年4月の数字を使った)。この金額を近距離便で使えば、かなり使い勝手が良くなるという仕組みである。
cf.月3往復といってもこのクーポン券は月をまたいで繰り越すことはできる。つまり4月と5月は1往復しかせずに6月は7往復という使い方は可能である(年度をまたぐのは不可)。ただし横峯議員の場合は平均的に月8回(つまり4往復)ほど搭乗している。
そして届けのあった那覇への飛行はほとんどない。数で言えば平成22年度に横峯議員は95回クーポン券を使っている。そのうち沖縄県に関係した使用は4回である。うち明らかに同一のフライトに2枚のクーポン券を使っているものがあるので便数でいえば3便にすぎない。羽田~那覇という便に限ればわずかに2便である。
平成23年度に関しては4月から8月19日の飛行まで44回のクーポン券使用が確認されているが、沖縄関係はゼロである。これでは沖縄県が「主たる生活又は活動の本拠地」とはとても言い難い。
このことは横峯議員も認めている。疑惑が取り沙汰されだした今年の9月26日付けで「地方住所」の所在地を沖縄県から宮崎県に変更している。確かにクーポン券の使用を見ても羽田~宮崎の使用が多いのは事実である。バレたから届けを直したと勘ぐられても仕方ないだろう。
実態のない沖縄県を登録して多額のクーポン券を支給されていたのが故意なのか過失なのかを断じることは難しい。しかしそれだけに本人の説明が必要である。
疑惑を受けた政治家は院の政治倫理審査会(政倫審)に自ら申し出て弁明することができることになっている。この政倫審は実は昨年から注目されている。小沢一郎元代表が「政治とカネ」の問題で政倫審(この場合は衆議院の政倫審だが)に出席するかどうかが焦点になったからである。
みんなの党を含め多くの野党は小沢氏の証人喚問を要求している。証人喚問は公開で実施され、偽証罪もある。一方、政倫審は原則非公開で、偽証罪もない。その点、政倫審の方がハードルが低い。そこで民主党も証人喚問は受け入れなくても、せめて政倫審での弁明には応じるかもしれないとして注目されていた。民主党の姿勢は揺れ動いたが、結局「小沢氏は起訴され司法の手続きの中にあるから」という理由で政倫審への出席さえ拒んでいる。
横峯氏の場合は、刑事訴追はされていない。だが倫理を問われていることは間違いない。航空機クーポン券だけではない。秘書の勤務状況に関わる疑惑も週刊誌などで取り沙汰されている。“刑事訴追されたら駄目、今も駄目”というなら、いったいいつ政治倫理審査会が活用されるのか。まずは本人自らが政倫審での弁明を申し出て、誰にでも分かるようにしっかりと説明責任を果たすことを期待したい。
「歳費カット法案などを再提出」
2011.10.28
歳費カット法案などを再提出
みんなの党は本日午前10時、参議院に国会議員歳費カット法案と国家公務員総人件費2割カット法案を提出した。前者の提出者は上野ひろし議員、後者の提出者は小野次郎議員である。
同様の法案はみんなの党として過去に何度も提出している。国会議員歳費カット法案は5回目の提出、国家公務員総人件費2割カット法案は3回目の提出となる。
国会は会期制をとっているので、会期内に成立しなかった法案は原則として廃案となる(継続審査という特別な手続きをとると次国会に持ち越されるが・・)。みんなの党は、これまでにもこうした法案を提出してきたのだが、他党が審議入りの意欲を見せないため、会期が終わると審議未了廃案というのを繰り返してきた。廃案になっても次国会が始まれば、同内容のものを再提出することは可能なので、回数が積み上がってきたわけである
。
以下、これらの法案の提出の記録を掲載する。
*国会議員歳費カット法案
提出日 提出者
第175回国会 平成22年7月30日 水野賢一
第176回国会 平成22年11月12日 松田公太
第177回国会 平成23年3月11日 上野ひろし
第178回国会 平成23年9月26日 上野ひろし
第179回国会 平成23年10月28日 上野ひろし
cf.法案の正式な名称は「国会議員の歳費、旅費及び手当等
に関する法律の一部を改正する法律案」
*国家公務員総人件費2割カット法案
提出日 提出者
第177回国会 平成23年8月5日 小野次郎
第178回国会 平成23年9月27日 小野次郎
第179回国会 平成23年10月28日 小野次郎
cf.法案の正式な名称は「国家公務員の給与の減額措置等に
よる国家公務員の人件費の総額の削減に関する法律案」
提出→廃案→再提出を繰り返すのは一見無駄な努力のようだが、「雨垂れ石を穿つ」という言葉もある。一歩でも前進すべく何度でも繰り返していきたい。
まして国会議員の歳費は、今月から事実上、月額50万円アップになっている。国会議員の中にも“身を削る覚悟”を口にする人は多い。しかし実際にはこのように逆行することが起きている。それだけに私たちが「歳費3割、ボーナス5割カット」の法案をあらためて提出した意味はあると思う
。
なお今月から50万円アップすることの仕組みについては9月28日のブログに詳しく述べているので、そちらを参照されたい。
月別アーカイブ
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年8月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2010年10月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年1月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年3月
- 2009年1月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年9月
- 2007年5月
- 2007年2月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年4月
- 2005年8月
- 2005年6月
- 2004年10月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年4月
- 2004年2月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月
- 2003年6月
- 2003年5月
- 2002年12月
- 2002年11月
- 2002年10月
- 2002年9月
- 2002年8月
- 2002年5月
- 2002年4月
- 2002年3月
- 2002年2月
- 2002年1月
- 2001年12月
- 2001年11月
- 2001年10月
- 2001年8月
- 2001年7月
- 2001年6月
- 2001年5月
- 2001年4月
- 2001年2月
- 2000年6月
- 2000年5月
- 1999年4月