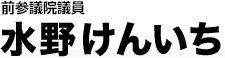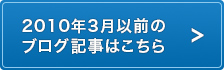『日曜討論』と雑感
明日朝9時からのNHK『日曜討論』に出演することになった。8政党による討論だが、各党幹事長代理クラスが出るという(より小さな政党は幹事長が出るようだが)。私もみんなの党幹事長代理として出席する。この番組に出るのは5月29日以来となる。
どうでもよいことながら以下雑感を少し。
これまで多くの政党は幹事長のすぐ下の役職を「幹事長代理」と呼んでいた。ところが最近、民主党にも自民党にも「幹事長代行」なる新たな役職が誕生した。民主党は野田佳彦代表になってから、自民党は今月になってからのことである。
「代理」が「代行」に改名したのではなく、幹事長と「代理」の中間に「代行」が新設された。つまり幹事長―幹事長代行―幹事長代理となるわけである。
私も以前、自民党の衆議院議員だったが、初当選後まもない小渕内閣の頃の資料を見ると、当時与党の自民党幹事長室の組織は以下の通りでかなりシンプルだった。
幹事長 (1人)
幹事長代理(1人)
副幹事長 (15人)
それが野党になるとまもなく幹事長代理が6名にまで増員されたり、今度は幹事長代行まで作ったりして、随分と複雑な組織になってきた。現在の機構図をみると上から、
幹事長 (1人)
幹事長代行 (1人)
幹事長代理 (2人)
筆頭副幹事長(1人)
副幹事長 (11人)
となっている。
民主党も似たようなもので、現在、
幹事長 (1人)
幹事長代行 (1人)
幹事長代理 (1人)
筆頭副幹事長(1人)
総括副幹事長(3人)
副幹事長 (15人)
である。
他の政党の機構図をあれこれいうつもりもないし、大政党の運営には私たち中小政党とは違った苦労があるのだろう。それに時代や状況に応じて組織のあり方を柔軟に改組することは決して悪いことではない。
ただ本当に「時代に応じて柔軟に改組した」のか、それとも単にポストを増設しただけだったのかが、ちょっとだけ気になる・・。
国会が使う電気について(その2)
~東電優遇に道理なし~
国会の電気代は7億8800万円となっている。これは議員会館や宿舎も含んでいるので議事堂本館と分館等に限れば3億5800万円になる。議員は別としても職員だけで衆議院には1700人、参議院には1300人働いているのだから大企業のようなものである。
電気契約の内訳を見てみよう。ちなみに国会議事堂は正面玄関から見て左側半分が衆議院、右側半分が参議院だが、電気は別々に契約している。議員会館は衆議院用に2棟、参議院用に1棟あるが、これも別々の契約である。そこで資料は両院から取り寄せた。
【衆議院主要建物の電気契約等一覧】
|
|
契約電力
|
使用電力量
|
電気料金
|
|
本館・分館等
|
3,480
|
11,983
|
205,195,833
|
|
議員会館
|
3,621
|
14,096
|
248,093,501
|
|
議長公邸
|
209
|
445
|
8,084,578
|
|
副議長公邸
|
34と20
|
93
|
2,016,018
|
|
憲政記念館
|
276
|
686
|
12,239,630
|
|
参観者バス駐車場
|
18
|
48
|
1,032,967
|
|
青山仮議員宿舎
|
22
|
141
|
2,504,289
|
|
赤坂議員宿舎
|
437
|
1407
|
22,419,125
|
(平成22年度実績。単位は契約電力はkw、使用電力量は千kwh、電気料金は円)
【参議院主要建物の電気契約等一覧】
|
|
契約電力
|
使用電力量
|
電気料金
|
|
本館・分館等
|
2,856
|
9,403
|
153,097,052
|
|
議員会館
|
3,300
|
6,358
|
105,669,442
|
|
議長公邸
|
302
|
260
|
4,726,285
|
|
副議長公邸
|
55
|
99
|
2,061,556
|
|
麹町議員宿舎
|
281
|
1,103
|
16,739,178
|
|
清水谷議員宿舎
|
61
|
309
|
4,323,530
|
(平成22年度実績。単位は契約電力はkw、使用電力量は千kwh、電気料金は円)
これらはすべて東京電力との随意契約である。現在、法律上は契約電力50kw以上のものは自由化されているため、いくらでも入札して安い電気を買うことができるにもかかわらずである。
電気代は合計すると衆参両院で7億8800万円になる。使用電力量は4600万kwhである。もっとも4600万kwhといってもすぐにはピンとこない。他の有名な施設と比べてみよう。帝国ホテル(日比谷)が5520万kwh、日本橋三越本館・新館が4502万kwhとなっている。
cf.帝国ホテルなどのデータは省エネ法の定期報告に基づく。
ただホテルやデパートと違うのは、国会は税金で運営されている点である。民間企業がどの電力会社からいくらで電気を購入しようと、その会社の判断である。だが国会の電気代は税金である以上、しっかりと監視の眼を光らせる必要がある。
入札の結果、東京電力が落札するというならば分かる。しかし入札さえせずに高い電気を買い続けるという理由はまったく説明がつかない。東電だけを優遇するのは道理が通らない。国会関連施設でも国会図書館はすでに入札の結果、新規参入事業者(PPS)のエネットが電気を供給している。国会図書館にできて国会本体ができないはずがない。
すでに参議院の事務方には「入札すべきだ」という私の考えは伝えてあるが、電気料金を含む国会の予算要求は正式には来年1月に決まることになる。まず衆参両院の議院運営委員会庶務小委員会で諮り、その上で議院運営委員会で決めることになる。私自身は現在、議院運営委員会の理事であり、庶務小委員会のメンバーでもある。改善が見られない場合には、しっかりと発言をしていかなければならないと思っている。
実はこの問題は国会だけではない。地方自治体もそうである。50kw以上の電気が自由化対象ということは、地方自治体の使う電気もかなりの部分は入札できるはずである。だがこれも遅々として進んでいないように見受けられる。
幸い今年の統一地方選などでみんなの党所属の地方議員も増えてきた。こうしたこともきちんと調査していきたい。そして問題があれば改善を迫っていきたいと思っている。
水野賢一事務所です
今週末、10月9日(日)のNHK「日曜討論」(午前9時より生放送)
みんなの党を代表して水野けんいちが出演いたします。
水野賢一 現在みんなの党 幹事長代理、参議院国対委員長
【主な内容】
・第3次補正予算案について
・復興財源のあり方について
・議員定数削減について
ぜひ、ご覧ください!
衆議院候補予定者2名発表!
~千葉7区と8区~
本日、夕方に渡辺喜美代表が千葉県庁で記者会見を開き、みんなの党の衆議院選挙区支部長2名を発表しました。支部長というのは端的にいえば、次期衆議院選の公認候補予定者です。その2名とは、
7区 石塚貞通(いしづか・さだみち)
8区 山本幸治(やまもと・こうじ)
の両名です。
ちなみに7区というのは松戸市北部、野田市、流山市で現職議員は民主党の内山晃(3期)氏です。なお自民党の斎藤健(1期)氏も比例区で復活当選しています。
8区は柏市(旧沼南町を除く)と我孫子市で、現職議員は民主党の松崎公昭(4期)氏です。一方、自民党の支部長は現在落選中の桜田義孝氏です。
みんなの党が新たに支部長に選んだ7区の石塚貞通さんは昭和42年4月20日生まれの44歳です。立教大学法学部を卒業後、野田市で司法書士を開業しています。
8区の山本幸治さんは昭和46年12月4日生まれの39歳です。東京大学教育学部を卒業後、ボウリング界に入りプロボウラーになるという異色の経歴です。
両名とも若くて、優秀で、志が高く、みんなの党の政策を推進する覚悟に満ちています。こうした人たちこそ次期国政選挙で二大政党に挑戦するのにふさわしいと思っています。その挑戦が実りあるものになれば新時代が切り開けるとも思っています。
すでに千葉県2区(八千代市、習志野市、千葉市花見川区)と6区(松戸市南部と市川市北部)の支部長は決定済みですから、本日の発表で県内の衆議員選挙区支部長は合計4人になりました。私自身も県内選出参議院議員として皆と力を合わせて進んでいく覚悟です。
国会が使う電気について(その1)
~入札しないままでよいのか~
国会議事堂も当然のことながら電気を使う。電球もあればエレベーターもある。その電気代は議事堂本館・分館等だけで3億5千万円となっている。
cf.衆参の議員会館や議員宿舎、衆参議長公邸などは含まない。これらをすべて含むと衆参合計で7億8千万円に上る。
ではこの電気はどこから買っているのだろうか。東京都にあるのだから東京電力だろうと考える人も多いだろう。結論からいえばYesである。だが今は東京であれば東電から買うに決まっているという時代ではない。電力は一部自由化されているので(まだまだ不十分だが)、一定規模以上の施設ならば東京にあろうと他の電力会社から調達することは十分に可能のはずである。現に各官庁の本庁ビルの電力購入先は以下のようになっている。
省庁名 庁舎名 落札者 入札金額
内閣府 内閣府本府庁舎 エネット 4499万円
財務省 財務省本庁舎 丸紅 9807万円
財務省 中央合同庁舎4号館 丸紅 11723万円
外務省 外務省本省 エネット 16497万円
経産省 経産省総合庁舎 丸紅 18650万円
経産省 特許庁本庁舎 Fパワー 31038万円
防衛省 防衛省本省 東京電力 91604万円
宮内庁 宮内庁本庁 丸紅 8708万円
農水省 中央合同庁舎1号館 エネット 13419万円
総務省 中央合同庁舎2号館 エネット 25457万円
国交省 中央合同庁舎3号館 Fパワー 15792万円
厚労省 中央合同庁舎5号館 エネット 25917万円
人事院 同上別館 Fパワー 2885万円
法務省 中央合同庁舎6号館 丸紅 34741万円
(平成22年11月25日現在。なお千円の単位は切り捨てた)
cf.入札金額とは落札価格から税を除いた価格を指す。
これを見れば分かる通り、ほとんどの省庁は東電以外から調達している。唯一、東電と契約している防衛省も何も最初から東電から買うと決めているわけではない。入札の結果、たまたま東電が落札したにすぎない。
では国会は入札の結果、東電が落札したのか。答えはNoである。いまなお随意契約を続けており、入札さえしていない。国会の支払いは言うまでもなくすべて税金である。競争入札で安いものを選ぶのが当然ではないだろうか。
なぜ随意契約なのか。事務方に聞けば「安定供給のためですが・・」と言葉を濁すが、原発事故後の経緯を見れば東電だと安定供給が確保できるというのはもはや神話にすぎない。国会だけは格安料金になっているということもなければ、電気の品質が格別違うわけでもない。
要はまったく合理的な理由はないのである。私の印象では“昔から買っているので、わざわざ変えるのも面倒だ”という程度のことである。また“入札で安い電気を購入する努力をすべきだ”と追及する議員もいなかったためである。私も衆議院議員時代にこの問題を少し調べたが、それほどしつこくは追及しなかった。今となっては反省の余地があるが、それだけに今度は声を大にして言いたい。「随意契約などは早急にやめるべきである」と。
国会内のどの施設がどれだけの電気を使っているかなどについては
次回のブログで。
水野事務所です。
水野のインタビューが、日本映像通信さんのHPにのりました。
↓下記のサイトを御覧ください。
http://www.mobacha.net/seito.html
「党役員に聞く」コーナーの「みんなの党」をご覧ください。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。
道路特定財源が一部復活!?(その2)
~業界の顔色を窺う各政党~
運輸事業振興助成法という業界助成法が成立し9月30日に施行されてしまった。内容は軽油引取税のうち一定部分(全国で合計200億円)は都道府県のトラック協会・バス協会に交付金として渡すというものである。
ただこの制度は今回まったく突然にできたというわけではない。似た制度は自民党政権下の1970年代から存在していた。それが民主党政権のもとで法制化され補強されたというべきなのである。
話は軽油引取税に暫定税率ができた1976年に遡る。この時、1リットルあたり15.0円だった軽油の税金は、暫定措置として19.5円に上がることになった。軽油を燃料としているのは主にトラックとバスである。当然、トラック業界、バス業界は「そんなに上げられたら困る」と主張した。そうした中、妥協策として、値上げはするが両業界に還元するということで落ち着いた経緯がある。そして同年11月に自治省(現・総務省)の事務次官が各都道府県知事に「値上げしたうち半分は各都道府県のトラック協会などに交付金として渡しなさい」という通達を出した。
ところが地方分権の流れの中で、通達の効力が弱くなってきた。2000年に施行された地方分権一括法では通達は単なる技術的助言であり、それに従うかどうかは自治体の判断と位置づけられる。そうなると都道府県の中にも「せっかくの税金をなんでトラック協会などに回さなくてはいけないのか。法律上の義務ならばともかく、中央官庁からいちいち通達で指示される筋合はない」という反発も出てくることになる。現に大阪府の橋下知事はトラック協会などへの交付金を削減して、別の分野に回した。当然のように業界は反発した。
一方で民主党は野党時代に暫定税率廃止を高らかに唱っていた。これらの業界からすれば大幅な減税になるため期待も高まっていた。しかし政権獲得後はこの約束も反故にされた。民主党からすると期待を裏切ったわけである。
そうした中で業界を慰撫するために浮上したのが交付金の法制化である。通達だと従わない自治体が出てくるので、今度は法律に明記して義務にしようというわけである(実際の法律では交付金は明確な義務ではなく努力義務になっている)。
野党第一党の自民党は元々業界の支援こそカネと票の命綱だと思っているので当然賛成である。それどころか“努力義務では足りない。明確に義務にしろ”という。例えば国会質疑で同党の片山さつき議員は「実際にはもう本当に義務付けたのと同じような形で運用していただきたいと思います」と述べている(参議院総務委員会・8月23日)。
前回のブログでも少し触れたが、私はこの交付金が全部悪いと言っているわけではない。たしかに安全対策や環境対策で有意義に使われているものもあるだろう。しかし必要な交付金なら一般財源から出せばよいだけのことである。「この税はこれに使わなければならない」と義務付ける特定財源的なやり方が問題だと言っているだけである。
この法律には別の大きな問題もある。地方分権に真っ向から逆行しているという点である。軽油引取税は都道府県税である。何に使うかは都道府県が判断するのが筋である。にもかかわらず国が法律で“この分は各都道府県のトラック協会・バス協会にまわせ”というのは余計なおせっかい以外の何物でもない。民主党が掲げてきた地域主権のスローガンが泣くというものである。
要はこの運輸事業振興助成法は筋の悪い法律としか言いようがない。こんな法案がろくに審議もされずに成立してしまった。審議は衆参ともに総務委員会で行なわれたが、その時間は衆議院が約10分、参議院も1時間弱である。このわずかばかりの審議時間の結果、みんなの党以外の全党が賛成する形で法案は可決成立した。
結局、業界の顔色を窺う政党ばかりでは、既得権益は打破できない。それどころか補強・強化されてしまう。しがらみのない、みんなの党の役割がここにもあると思う。
道路特定財源が一部復活!?(その1)
~既得権益擁護の立法を許してよいのか~
9月27日のブログで道路特定財源を一部復活させるかのような法律が先月成立したと書いた。本日は、その法律「運輸事業振興助成法」について触れたい。
まず自動車燃料には消費税以外に次のような税金がかかっている。
ガソリン・・揮発油税、地方揮発油税(二つを総称してガソリン税と呼ぶ)
軽油 ・・・軽油引取税
LPガス・・石油ガス税
cf.数は少ないが天然ガス車もあるが、この天然ガスは課税されていない。
数年前まではこれらの税金は道路関係にしか使えなかったため道路特定財源と呼ばれていたことも前のブログで述べた。このうちガソ
リン税と石油ガス税は国税だが、軽油引取税は都道府県税である。
運輸事業振興助成法は、この軽油引取税のうち一定部分は必ず都道府県のトラック協会・バス協会に交付金として回すようにするという法律である。一定額というのは全国で年間200億円である。千葉県の場合だと7億円余りになる。千葉県トラック協会と千葉県バス協会に毎年合計7億円強が交付されることになるわけである。
この税金は必ずこれに使わなければならないというのが特定財源である。軽油引取税のうち200億円分はトラック協会・バス協会に交付しなければならないという仕組みはこれに似ている。先に特定財源が復活しつつあるとしたのはそういうことである。
特定財源はなぜ問題なのか。無駄使いの温床になるからである。予算には限りがある。それだけに本当に必要な分野から優先順位をつけながら決めるのが本来の姿である。そこで本当に必要なのかどうかを厳しく査定する。ところが特定財源はそうなっていない。査定と関係なく予算が最初から入ってくる。そうなると何が起きるか。「税収があるから使い切るまで使う」という現象である。だからこそ無駄の温床として道路特定財源が廃止されたのである。それがこうした形で部分復活するというのでは骨抜きと言わざるをえない。
もちろんトラック協会やバス協会は大喜びである。必ず一定額の交付金が保証されるのだから当然だろう。法律名は「運輸事業振興助成法」だが実態としては「業界助成法」なのである。こうした業界団体は安全対策や環境対策のために交付金を有効に使っていると主張する。私もそれが間違っているというつもりはない。しかしそれならば必要額を査定した上で、県が交付金として出せばよいだけである。最初から何億円を交付すると決めているのでは単なる既得権である。
環境対策費なども年々変動があるのが普通である。新たな規制によって、ある年の対策費は膨れ上がるかもしれない。しかしそれが一段落すれば予算は減るはずである。にもかかわらず毎年一定額を必ず保証するという仕組みには疑問がある。せっかくの税金である以上、その時その時の必要性の高い分野に自由に融通すべきなのであり、特定分野だけを聖域化すべきではない。
こうした問題の多い運輸事業振興助成法は8月24日に成立し、明日(9月30日)施行される予定である。国会審議ではみんなの党だけが反対し、他の政党は民主・自民・公明・共産・社民・たちあがれ日本・国民新党などがいずれも賛成に回った。
なぜこうした妙な法案が出てきたのか。
その背景などについてはまた次回のブログで。
国会議員の歳費カット終了
~こっそり終わってよいのか~
別に「ええ格好をする」わけではないが、私たちみんなの党は国会議員の歳費3割、ボーナス5割カットを掲げている。国家財政多難な折、まず議員自身が給与削減をするのは当然だと考えるからである。また公務員総人件費の削減も唱っている以上、「まず隗より始めよ」ということで議員が身を切る必要もある。その覚悟を示さずに人に痛みを伴う改革を強いることはできない。
公務員総人件費といえば民主党も前回総選挙で2割削減をマニフェストに掲げていた。そうすると年間に国家公務員分だけで1兆円が捻出できると言っていた。ところがこの約束も例によって果たされていない。前の国会に政府が提出してきた法案では2割削減がいつのまにか8%削減に縮小された。しかも法案はいまも成立していない。前進しない言い訳はいろいろできよう。だがその大きな理由は民主党政権に身を切ってでも進めていくという覚悟が感じられないことだと思う。
さて国会議員歳費に話を戻すが、東日本大震災後、歳費は期限付で削減された。毎月50万円削減が6か月継続というものだった。みんなの党はそれ以前から、より大幅な歳費カットを主張し法案も提出している。それに比べれば小幅で不十分とはいえ削減自体には反対する理由もないので私たちもこれに賛成した。
その6か月が9月末をもって切れる。つまり10月からは通常に戻るわけである。こういうことはこっそりと終わりたいという人たちもいるだろう。しかしそれだけにあえて事実を記さなければならない。以下、論評抜きで客観的事実だけを述べておく。
2011年
3月11日 みんなの党が歳費カット法案を提出
・・内容は歳費3割、ボーナス5割カットというもの
大震災の発生直前の午前11時45分に提出
3月31日 歳費を6か月間、月額50万円削減する法案が
提出され、同日中に、衆参本会議で全会一致で可決成立する
・・法律の正式名称は「平成二十三年東北地方太平洋沖地
震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の
月額の減額特例に関する法律」
提出者は衆議院の議院運営委員長
8月31日 通常国会が閉会し、それに伴い、みんなの党が
3月11日に提出した法案は審議未了廃案となる
9月26日 みんなの党が歳費カット法案を再提出
・・内容は3月11日に提出したものと同じ
10月10日 国会議員への10月分の歳費支給日(予定)
・・10月からは減額措置が終わるので満額支給に戻る
なお国会議員の給与は歳費という独特の呼び方をするので一見、
年俸のようにも聞こえるが、毎月10日に支払われる。
また衆議院議員と参議院議員の貰う額はまったく同じである。
歳費月額は、
議長 217万円
副議長 158万4千円
議員 129万4千円
cf.ただし4月~9月はここから50万円が削減されていた。
期末手当(ボーナス)は、
6月30日 12月10日
議長 440万5100円 487万7075円
副議長 321万5520円 356万0040円
議員 262万6820円 290万8265円
それ以外に各議員には文書通信交通滞在費が毎月100万円支給される。
こちらの支給日は毎月10日に50万円、月末日に50万円となっている
(4月と12月は25日に50万円)。
cf.4月~9月の50万円減額はあくまでも歳費月額への
臨時措置であり、期末手当と文書通信交通滞在費の支給額には
一切影響がないようになっていた。
暫定税率廃止はどうなった(2)
~特定財源廃止のはずだったのに~
前回のブログでは民主党が「暫定税率廃止」を掲げながら、実行したのはまったく逆方向だったことについて述べた。ここではまず私自身が暫定税率についてどう考えるかについて触れておきたい。
実は私はガソリン税を下げろという立場に与したことはない。
とはいえ「暫定です」と言って30年以上も本則よりも高い税率を課してきたのはおかしいと思っている。だからこそ「暫定です」と言い続けるフィクションをやめて、1リットル=53.8円を本則にすべきだと言ってきた。
そうした私の考えからすると民主党政権が税率を維持したこと自体が間違いだとは思わない(もちろん総選挙の時に減税を約束して票を集めておきながら、それを平然と反故にしていることはけしからんと思っているし、そんな約束は最初からするなとは思っているが・・)。
私がかねてから問題だと思っていたのは税率よりもむしろ使途の方だった。ガソリン税や軽油引取税は道路にしか使えない税金だった。余っていようが余っていまいが関係なかった。医療や年金や教育や環境の財源が足りなかろうが、そんなことも関係なかった。とにかく“道路にしか使わせない税金”だった。そこで「道路特定財源」と呼ばれており、道路族にとっては大切な税金だったわけである。
一方、私は“道路にしか使わせない”などという仕組みはおかしいと主張していた。もちろん道路に使うことを全部駄目だとは言わないが、道路にしか使わせないなどという馬鹿な税金があるかと唱えたわけである。そもそも税というのは、必要があれば福祉でも治安でも文教でも自由に使えるべきだからである。このように何にでも使える税金にすることを一般財源化という。当時私が所属していた自民党では一般財源化論者は少数派だったが、私はその急先鋒の側に立っていた。
その頃の民主党、自民党道路族、私の主張を表にしてみれば以下のようになる。
暫定税率 使途
民主党 廃止 一般財源
自民党道路族 維持 特定財源
私 維持 一般財源
それでも自民党政権末期の2009年度から道路特定財源は廃止された。全額を道路に充てると法律に明記されていた規定がなくなり、何にでも自由に使えるようになった。道路族の抵抗を押し切ってよく改革できたものだと思っている。
しかし、なんと民主党政権下でこの点でも逆行が進んだ(自民党も加担しているが・・)。特定財源を一部復活させるかのような法律が先月成立したのである。運輸事業振興助成法という法律である。みんなの党だけが反対したが、民主党・自民党などの賛成により圧倒的多数で可決されてしまった。この法律の問題点についてはまた別の機会で。